メルマガ登録

DOORS編集部(以下、DOORS) はじめに小野教授の研究について教えてください。
小野 譲司氏(以下、小野氏) 私は経営学の領域で、サービス産業を中心とした市場分析とマーケティングを専門に、研究を行っています。マーケティング研究では、消費者の視点に立ち「どういうお客さんがそのサービスや商品を使うのか」という消費者行動について、考察することが一般的です。私は、日本中のさまざまなサービスを対象として、顧客体験やリピーター醸成などのトピックについて、データ分析とフィールドワークに基づいて、研究しています。
DOORS 昨今、社会環境や人々の購買行動が変化していると聞きます。小野教授のお考えとしてはいかがでしょうか。
小野氏 デジタルという側面から見ると、この20年間で顧客接点が増えたことは、紛れもない事実です。サービス分野について見てみると、その変化にはいくつかの段階があったことがわかります。
例えば、宿泊や航空といった旅行業界では、旅行代理店を介し、あるいは直接予約を取ることが、それまで一般的な方法でした。しかし、2000年代中頃からECサイトが台頭し、さまざまなサービスがリリースされます。旅行業界がECと相性のいい分野であったことに加え、こうしたサービスについてコストパフォーマンスが良いと消費者から捉えられたことで、ECサイトを中心とした旅行予約が一気に普及しました。
特に発展途上国への旅行需要が増えたことで、旅行業界全体で右肩上がりの成長を見せています。しかし、実際に大きな恩恵を受けたのは、伝統的な旅行業界のプレイヤーというよりも、ECサイトを運営するIT系企業が目立っていました。

その後、2010年代半ばから、伝統的なプレイヤー、つまり、本業であるホテルや航空会社の逆襲が始まります。「最低価格保証」を謳い、自社サイトやアプリを活用したコミュニケーションが加速しました。ホテルでは企業買収による業界再編が進み、一つのブランドでリゾートからビジネスまで対応する形態も見られるようになりました。これらの戦略の狙いの一つは、自社ブランドでのLTV(顧客生涯価値)の向上です。
他方、航空業界では旅客機の小型化が進んだことで、それまでECサイトで安く売られてきた空席が、徐々に減少していきました。ECサイトとの価格差が縮まるにつれて、次第に消費者も航空会社の自社サイトやアプリから直接予約するようになっていったのです。日本市場について見れば、団体旅行から個人旅行への旅行形態の変化が、デジタルでつながった予約へと段階的にシフトしたのではないかと思います。
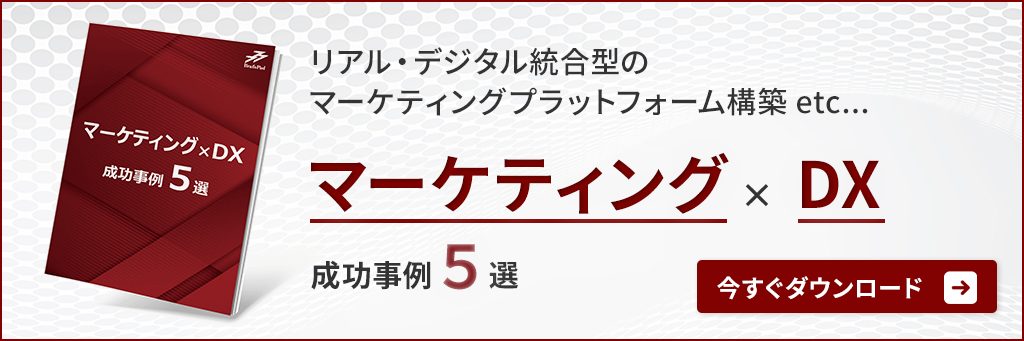
DOORS EC化というと、パンデミックの影響で小売業界も同様だと思います。こうした状況をどう捉えていますか。
小野氏 小売業界では大手ECモールが台頭してきています。しかし、データを見るとその影響力は限定的です。ECの利用は都市部や若年層には普及したものの、一方で実店舗も依然として残っています。
確かに、小売業界でもデジタルが普及しました。商品の情報収集から購入に至るジャーニーのあらゆる場面にデジタルが浸透し、消費者はそれぞれ好みのチャネルから商品を探すようになっています。

ところが、これによりECサイトに偏ったわけではなく、「消費者はECサイトと実店舗を組み合わせながら、場合に応じて使い分けるようになってきている」と考えられます。例えば、スーパーでいえば「加工食品を買う店」と「生鮮品を買う店」を分ける、といった具合です。これまでは立地に左右されるため、一つ店舗で買い物を済ませることもありましたが、最近ではどこか一つの店舗に集中せず、分散して買い物する傾向が見受けられます。
また、商品の選択肢も多様化したことで、日常生活で使うような「これでいい商品」と、あえてお金をかけたい「これがいい商品」という商品の選別も進んできています。加えて、パンデミックの影響でECサイトでの買い物も普及しました。
このようになると、ブランドの実店舗で商品を買うという行為には、他と特異点や自社の独自性、さらには「わざわざ店舗に足を運ぶ価値」が求められるようになってきています。
DOORS そうした流れから、顧客体験の重要性につながっていくのですね。
小野氏 そうですね。私の講義で学生たちに、あるハイブランドのジャケットを見せたことがあります。それについて学生たちに意見を聞くと「ファストファッションで十分だ」という声が多く聞かれました。安くてコストパフォーマンスの良い商品が広まったことで、日常生活ではそれで事足りてしまうのです。特にこの約10年間、コスパについて意識する消費者が多かったと思います。
ところが、次第に消費者も目が肥えてきたことで、コスパがいいだけでは買う理由にならなくなってきているのです。おしゃれをしたい時に着る服には、相変わらず需要があります。高い商品であるなら、買うに値するようなデザインやユニークさ、機能性といった、独自性のある商品やブランドが求められ、生き残っていくのではないかと思います。
DOORS そうした価値が求められるなか、顧客体験としてどういったことが有効なのでしょうか。
小野氏 人の感情が顧客体験に与える影響は、マーケティング研究でも注目されているテーマですが、私も重視すべきだと考えています。人は何かを想起するときに、過去の記憶がフラッシュバックすることがよくあります。感情の伴った体験は想起されやすいため、選択肢の候補に入る可能性が高くなるのではないか、というのがその基本的な問題意識の一つです。そのため、人をワクワクさせながら不安を取り除きつつ、消費者の記憶に残るような工夫が求められます。
顧客満足度の調査では、テーマパークやミュージカルなどのエンタテイメント業界については、他の業界と比較して満足度が高くなる傾向にあります。エンタテイメント業界は、人々に楽しさやワクワク感を提供する産業です。加えて実際に「体験した後」にも、その体験を人に話し、お土産を配るといった「顧客体験」があります。こうした体験を通して、消費者に高い満足度を与えていることで、「また行きたい」と消費者に思わせるのかもしれません。
最近では、ECサイトやアプリが普及するにつれて、利便性が追求される傾向にあります。それにより実店舗に行く前から、商品やサービスについて把握できることが多くなりました。しかし、実店舗に行って初めてできる体験も、楽しさを生み出す一つの仕掛けになります。そこで、全て把握できるようにするのではなく、ECサイトでは「あえて隠す要素」を作ることも一つの手段といえるでしょう。

例えば、北欧の大手家具メーカーの実店舗では、レジを通った先で50円のソフトクリームを販売しています。これは、最後の体験が人の記憶に強く残る特徴を使った、「決め打ち」のような施策です。その記憶があるから「あそこは楽しくて安い」という印象を消費者に与え、実店舗に来る価値につなげているのだと思います。
DOORS 顧客体験を語る上で、LTVは重要なトピックの一つと言われますが、この点についてはどう思われますか。
小野氏 確かに、LTVの向上は重要な施策の一つです。一方で、LTVだけに執着せず、そこに現れにくい要素も分析、検討することが重要だと考えています。例えば、BtoB業界に目を向けてみましょう。大口の常連客ほど価格交渉を迫られるが、新規顧客の方が正規の価格で応じてくれる、ということが起こりがちです。しかし、大口のお客様と取引を通じて、業界のトレンドを学べたり、プレゼンスにつながったり、というように「取引金額に現れない別の価値」もあります。
このように実際の取引実績から企業にもたらされる利益だけではない、顧客からもたらされるさまざまな価値を、研究領域では「エンゲージメント」として扱っています。エンゲージメントといってもプラスの反応だけでなく、クレームのようなマイナスの反応も、そのうちの一つです。自社に対して厳しい指摘をされるお客様は、会社としての資産価値があります。もし関心がなかったら、そうしたコメントはもらえないからです。このように金額や数字に換算しにくいような側面も含め、あらゆる視点でお客様を捉えることが重要なのです。
DOORS デジタルマーケティング界隈では、さまざまなツールが登場しています。それらのツールに対して小野教授が率直に思うことがあれば教えてください。
小野氏 機能面の充実が先行して、ツールを導入したユーザー側が「何をしたいのかわからない」という事例が散見されます。こうした状況の中では、「何を目的にするかという課題設定」こそ重要です。
例えば、ある企業の方から「カスタマージャーニーマップを描くワークショップに参加したが、その時はわかった気がしたが、会社に持ち帰っていざやってみようとすると頓挫する」という話を聞きました。そのような悩みは珍しくなく、「実際にマップを描いたものの、その後どうするのかわからない」という企業は少なくないようです。こういった場合の課題は、部門の枠を超えて対応するという方針が決まっても、「統括する人が設定できない」という組織体制の点にもあります。また、それぞれの部署が別々の行動指針に基づいて動いているため、次に何をすればいいのかわからなくなっていることもあります。
データをとって実証研究をしたわけではなく、あくまでも仮説にすぎませんが、顧客体験で成功している企業の多くは、小さな成功体験を積み上げて横展開させていくような、地道な取り組みを続けている、という印象を持っています。顧客体験を向上させるには、スモールスタートで始め、継続することが重要なのかもしれません。 逆にブレインパッドさんにご質問ですが、最新のECツールの動向はどのような状況になっているのでしょうか。
DOORS ECサイトにおいて、思わぬ商品との出会いを演出する「セレンディピティ」の実現を目指している状態ですが、既存の顧客行動データだけでは限界があります。そこで注目しているのが、実店舗で働く「ベテラン販売員の接客ノウハウのデータ化」です。このノウハウと既存のデータを掛け合わせ、体験をパーソナライズすることで「セレンディピティ」の実現を目指しています。
小野氏 パーソナライズという観点では「人の要素を入れていくこと」が重要なテーマになると思います。最近のECサイトには、チャットボットと一緒にアバターを表示していることがあります。アバターを表示する企業の担当者になぜ人の要素を入れたのかと聞いて回っていますが、「アバターを置くことで、人間的なおもてなしを表現している」という話をされる方が多い。消費者からもチャットボットだけでなく、アバターがあることで、より相談や問い合わせしやすくなっている、というのがその理由のようです。逆に、人の要素があることで、相談したいパーソナルなことをチャットに書き込みづらくなってしまわないかという疑問も湧きますが、いずれにせよAIやロボットに人の要素をつけることには正負の意味があると思います。
また、人の要素には「マジック」があると注目しています。例えば、車のような高価な商品を買うとき、買う商品が決まっていても決断を躊躇する瞬間があります。そうした時に、販売員さんから「いいお買い物ですね」という一言があることで、決断できるのです。このように、人から言われると安心して買い物ができる、という現象がよくあります。
これまでのECサイトは、利用する人の多くがリテラシーの高い方々だったと思います。しかし、パンデミックの影響でさまざまな人がECサイトを利用するようになりました。そうした背景から、「そのお客様に合う商品をレコメンドする」だけでなく、何か感情を揺さぶるような要素が求められているのだと思います。
感情の琴線に触れるような接客は、実店舗で販売員の方々が行ってきたことです。今後のECサイトには無機質なレコメンドではなく、「人の要素が加わったパーソナライズ」な体験が求められるのではないでしょうか。

