メルマガ登録
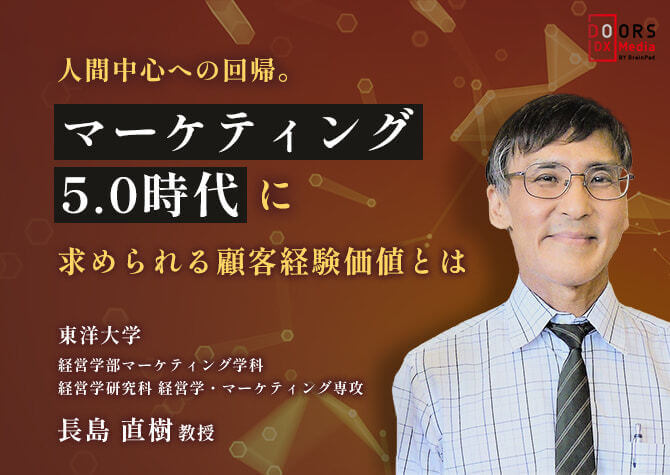
飛躍的なIT技術の進化に伴い、人々の生活、考えや価値観の多様化がもたらされた現代。その変化は消費者の欲求、行動原理、マーケットにも大きな影響を与えている。商品・サービスを提供する企業が、消費者とのタッチポイントを持とうとしたとき、マーケティングという概念はどのように変化し、❝現在地❞はどのように捉えるべきなのか。今回は「マーケティング5.0時代に求められる顧客体験価値」をテーマに、東洋大学経営学部マーケティング学科の長島直樹教授にお話をうかがった。
長島 直樹 氏
東洋大学 経営学部マーケティング学科 教授。東京大学 経済学部卒業、米国デューク大学大学院修了(経済学修士)。日本経済新聞社、富士通総研(経済研究所上席主任研究員)を経て、東洋大学に着任。専門分野は、サービスマーケティング、グローバルマーケティング。主にサービスの多国籍展開、海外進出の意思決定プロセスを研究する。著書に『Rで統計を学ぼう!文系のためのデータ分析入門』『ビジネス心理 検定試験公式テキスト 第3巻 マーケティング心理編』(共著・中央経済社)などがある。
DOORS編集部(以下、DOORS) フィリップ・コトラーによる「マーケティング5.0」という新しい言葉も出てくるなど、今マーケティングの概念は大きく変わろうとしています。このマーケティング5.0の話をする前に、はじめに長島教授が専門とされているマーケティングという学問について、その概念や近年のトレンドについて教えてください。
長島 直樹 教授(以下、長島教授) 結論から申しますと、マーケティングの”本質”そのものは昔から変化していないと考えています。例えば、ピーター・ドラッカーは「企業の唯一の目的は顧客の創造である」と言いました。これは必ずしもマーケティングに焦点を当てた言葉ではありませんが、マーケティングをシンプルに、ひとことで言えば、昔も今もこのドラッカーによるステートメントに集約されると私は思っています。
とはいえ、今日に至るまで、マーケティングに対する考え方は時代に応じて徐々に変化してきたことも事実です。その変遷を振り返ることは、マーケティングの現在地を確認する手がかりになるかもしれません。
マーケティングの歴史はまだ100年程度で、紀元前から2000年以上の歴史を持っている自然科学や哲学と比較すれば、学問としてはまだまだ幼児のようなものです。自然科学・哲学・医学・法学などは「どうやって生きていくか」「どう治めるか(統治するか)」といった「存在にかかわる」テーマが中心ですが、マーケティングは誤解を恐れずに言えば「どう豊かにするか?」が目的になります。
マーケティングの歴史は経済学よりもさらに短いですが、その考え方の変遷を思想史のようにたどってみるのは面白いですね。一例として、AMA(American Marketing Association)による「マーケティングの定義」が参考になります。
※AMA(American Marketing Association)
米国マーケティング協会。世界最大のマーケティング組織。本部はシカゴにあり、世界各国から実務家や関連分野の研究者が加入している。
第二次世界大戦前からたどるなら、1935年に発表された定義では、マーケティングは「生産地点から消費地点に至る事業活動」と捉えられていました。そして戦後となる1960年の定義では「生産者から利用者への財の流れを方向づける活動」と記されています。戦前と戦後に変化した点としては”地点”から”者”へと、「人」を中心にした内容に変化したことです。また、「財の流れ」の”財”の中には、モノだけでなくサービスも含まれていると考えられます。
DOORS それは”買い手主導”のマーケティングに変化したと解釈してよいのでしょうか。
長島教授 おそらく1960年代は、買い手主導ということではなく、企業主導(企業から消費者への働きかけが中心)であったと想像しています。1935年は「生産地点から消費地点」だったのが、1960年では「生産者から利用者へ」と人中心に変化しているということに過ぎないと思います。
1980年代中頃になると、マッカ―シーのいわゆる4P(プロダクト=商品、プライス=価格、プレイス=流通チャネル、プロモーション=広告・宣伝・広報)の枠組みがベースになります。「財・サービス等のコンセプト創生・価格・プロモーション・流通にかかわる計画と実行のプロセス」という表現が使われています。
2000年代に入ると「4P」という言葉は消えて「価値創造活動」という表現になります。大きな変化としては、「顧客」に加えて「ステークホルダーにも恩恵をもたらす活動」としている点、「顧客関係の管理を含む」とする点が重要でしょう。つまり、企業の社会的責任論(いわゆるCSR)が浮上するとともに、新規顧客開拓だけでなく、顧客維持を目的とする「リレーションシップ・マーケティング」が重視されるようになったことが反映されています。
「顧客関係の管理」は、具体的手法としては、データベースを使ったCRM (Customer
Relationship Management) として実践される場合が多く、顧客を個別に管理するという意味で、1 to 1(ワン・トゥー・ワン)マーケティングもほぼ同義です。ドラッカーの「顧客創造」に加えて「顧客維持」という視点が加わったわけです。
そして2000年代後半になると、マーケティング対象はステークホルダーに留まらず「社会全体」まで広がります。定義は、社会全体に対する「価値の創造、提供、交換を行う活動や仕組み」と変わり、現在に至ります。以上が、AMAの定義を通じてみた場合の「マーケティング」概念の変遷です。
DOORS 2000年代後半以降のマーケティングの概念では、対象が”社会全体”へと広がるに伴い、考え方もより抽象的な内容へと変化して、ある意味つかみどころがなくなっていきます。
長島教授 そうですね。変わらず一貫している考え方は、「組織・企業が行う価値創造活動」を中心に据えている箇所でしょう。「顧客創造・顧客維持」と言っても内容は変わらないと思いますが、少し具体的に言えば、マーケティングとは「企業が顧客との架け橋を考えるプロセス、活動」と言えるのではないでしょうか。具体的には、市場調査、商品開発、広告宣伝を含むブランド・マネジメント、このための組織の構築・運営――こうした活動がマーケティングの中心になると思います。
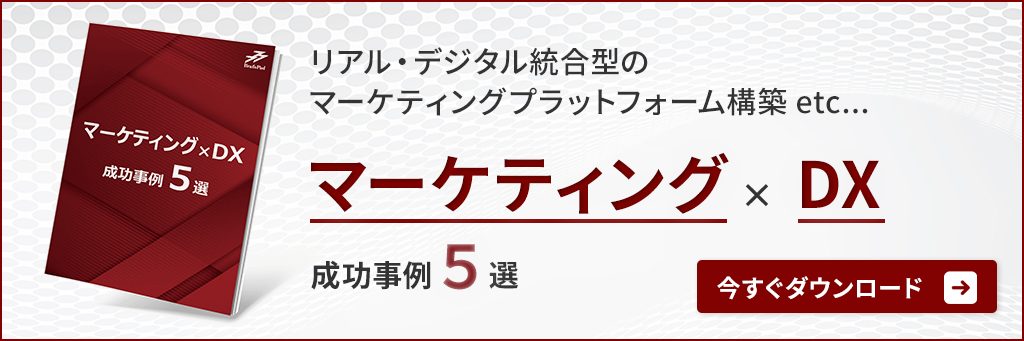
DOORS こうしたマーケティングの思想史をたどってみると、マーケティングが対象とする適用範囲が当初のそれとは大きく拡大してきていることがわかりますね。
長島教授 そうですね。新規の顧客開拓に加えて顧客維持がフォーカスされると同時に、マーケティング対象が「顧客」から「ステークホルダー全体」を含むようになり、やがては「社会全般」に広がっていることが定義の変遷から読み取れます。
対象範囲拡大の背景には、現代に生きる生活者意識、つまり社会意識の変化があると思います。近年は「環境・人権・働き方・デジタル技術・多様性」などが生活者の意識として浸透し、消費行動もこれらの影響を大いに受けるようになりました。こうしたトレンドがマーケティング概念にも反映されているということでしょう。
DOORS なるほど。
長島教授 「意識変化」を最もよく表しているのは「意味的消費」の浮上で、近年その重要性がますます高まっていることが消費者の意識変化を特徴づけていると思います。商品の機能や使い勝手と同等に、場合によってはそれ以上に、商品の背後にあるストーリーや、それらを生産する企業の社会的存在意義が問われるようになったのです。
企業側からみれば、CSR(企業の社会的責任)を単に慈善活動と捉えることは間違いであり、今やマーケティングに不可欠の要素となったということでしょう。「カンヌライオンズ」のセッションでは、すでに2010年代中頃から、「エシカル消費」や、「ブランドパーパス」というテーマが中心になっています。
※カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル
1954年に設立された毎年6月に南仏カンヌで行われる世界最大規模の広告・コミュニケーションフェスティバル
カンヌライオンズ日本公式サイト(https://www.canneslionsjapan.com/)より
しかし、「エシカル消費」や「ブランドパーパス」を標榜する企業の思惑が必ずしも、消費者に訴求できていないという傾向は、注目すべき点でしょう。2022年のカンヌライオンズでは、「企業ブランドへの信頼度が低下してきている」という報告もあります。
DOORS それはどのようなことを意味しているのでしょうか。
長島教授 企業のイメージ戦略として「社会性」を打ち出すことに対し、消費者が非常に懐疑的になっているということを意味しているのではないかと私は考えています。単なるイメージ戦略として自社の社会性をアピールしても、それは消費者には簡単に見透かされるということでしょう。具体的な施策やその成果を社会や消費者に説得力を持って訴求できないようであれば、単に企業のポーズであると思われてしまうということだと思います。
DOORS 興味深いお話ですね。こうした一連の流れ、つまり「意味的消費」の重要性や企業による「ブランドパーパス」の重視などは、近年のデジタル技術の進化と関連性があるのでしょうか?
長島教授 関連性は確実にあると思います。やはり大きいのはスマートフォンとSNSの普及です。影響力のある考え方、つまり注目に値する内容を持っていることが前提ですが、こうした「思い」や「考え方」が一瞬にして社会で共有される状況になりました。そしてこうした共感が社会のマジョリティに共有されれば、消費者意識・社会意識の変化につながることは容易に想像ができます。
DOORS マーケティングの定義や考え方の変化は、デジタル技術の進歩や社会の変化によってもたらされた側面も大きいと言えそうですね。
長島教授 消費者ニーズという面からみて、先ほど「意味的消費」という言葉を使いましたが、モノの不足が意識される時代は「機能的価値」が中心でした。日本なら高度経済成長期で、「三種の神器」や「3C」のような新製品の新たな機能が生活を豊かにし、圧倒的な存在感を持っていました。経済が成熟するにつれ、経済活動や消費生活の中でサービスのウェイトが高まり、「情緒的価値」の重要性が指摘されるようになりました。
繰り返しになりますが、現在は加えて「意味的価値」が重視されるようになったということです。「自身の購入対象の商品がどのような背景を持っているのか」「その商品を購入・消費する自分を好きになれるのか」ということが本質です。「意味的価値」の浮上は、先ほどお話しましたように、スマホやSNSの普及と無縁ではないと思います。消費者の思いや共感の共有速度が劇的に高速化したことが大きく影響しています。
DOORS フィリップ・コトラーは、これまで「マーケティング1.0〜4.0」のようにマーケティング概念をアップデートしてきています。近年は「マーケティング5.0」を提唱しています。その中で、「デジタル技術は活用しつつも、その対象や目的はあくまで人中心に立ち返ろう」という考え方があるような印象がうかがえます。共通しているのは、DX(デジタル・トランスフォーメーション)もマーケティングも「人間中心に回帰」ということではないでしょうか。このあたりは、どのように考えていますか?
長島教授 コトラーのマーケティング1.0〜3.0までは説得力のある考え方だと思います。4.0もわからなくはありません。1.0については、機能的価値というニーズに対応したマーケティングの考え方です。2.0は情緒的価値の浮上に対応しています。つまり、商品の機能性にプラスして、他人との差別化や個性を表現する手段としての価値提供を考えようということです。3.0については、商品背後にあるストーリーや、企業(生産者)が持つ社会的意義まで問われる状況に対応し、意味的価値を訴求するマーケティングの必要性を内容としています。
おそらく、このマーケティング3.0という考え方が生まれた段階で、技術的進化との密接な関連はすでに存在していたはずです。そこから時代はさらに進んで、デジタルネイティブやZ世代と呼ばれるような世代が消費者層として大きな割合を占めるようになりました。その少し上のミレニアル世代まで含めて、日常的にデジタルを使いこなしています。少なくともデジタルなしの生活は考えられない世代なのではないかと思います。
このような状況を反映し、マーケティング4.0は「企業と顧客のデジタル・タッチポイントを活用することにフォーカスすべき」という意味でアップデートした考え方なのでしょう。デジタルデバイスを介したユーザーのコンテンツ閲覧履歴・商品購買履歴、レビューの発信履歴などさまざまなタッチポイントを介して、企業は消費行動を逐一収集・蓄積ができるようになったわけで、これをいかに分析し、活用するかが大きな課題となっています。
DOORS なるほど。そこから、最新のマーケティング5.0に移り変わっていくわけですね。
長島教授 マーケティング5.0については、私は十分に理解できていないと思いますが、コトラーの「マーケティング5.0」をあらためて読んでみて、1.0から4.0と比べて5.0は概念がそれほど明確でない、というのが率直な感想ですね。
DOORS 確かに本書の提唱するマーケティング5.0では、その概念がより抽象的なものになっている印象を受けます。
長島教授 私自身、理解不足の可能性も踏まえた上で、個人的感想を述べるなら「マーケティング5.0という考え方・分類法は、今後20年、30年にわたって生きているようには思えないのです。もちろん、コトラーを語れば、今後数年間は顧みられるのかもしれませんが・・・・。
私の想像では、コトラー先生はとても包容力のある学者で、実際に若い世代の考えや発信をサポートしています。実は、私の家内が80年代にノースウェスタン大学のビジネス・スクール(ケロッグ・スクール)でコトラーの講義を受けた生徒の一人なのですが、その際に日本のCMをいくつか集めてきて、授業内でプレゼンを行ったとき「それすごく面白いね!アメリカの学生と一緒に、アメリカのCM事例集と併せて本を出版してみたら?」と、とても賞賛してくれたそうです。
こうしたエピソードからも、コトラーは若い人の新しい考え方などにとても寛容な方だと思います。マーケティング5.0について言えば、コトラーが若い研究者をバックアップする意味も含め、書籍化されたものではないかと想像しています。
DOORS これまでのお話をうかがって、デジタルがこれだけ生活に根付いた現代において、技術開発、促進や利用を”人中心”へ、あらためて向き直していることを感じたような気がしました。例えば、技術面では我々が日々呼吸するように利用しているGoogleの検索エンジンだと、ユーザーの検索意図・ニーズに沿った最適なリターンや提案ができているのかと言えば、必ずしもそうではなく、まだまだ改良の余地があります。
デジタル技術がジレンマに陥っているという現象が多少なりともあると思いますが、これと同様にマーケティングにもデジタル化によるジレンマが存在しているのではないかと思います。マーケティングに有用とされるMA(マーケティングオートメーション)ツールのようなものも世に多く出てきていますが、顧客の創造・維持という観点で言うと、これまで変遷をたどってきた”マーケティング”に照らし合わせて考えたとき、それらがどれほど本質に沿っているものなのか、長島教授の肌感としてこのあたりの印象として感じることはありますか?
長島教授 例えば、Googleはネット広告の最適化に向けたA/Bテストと微調整を頻繁に行っていると聞きます。広告の位置、文章と図を左右のいずれに配置するか等々とクリック率、滞在時間、コンバージョンレートなど数百万単位のデータに基づいて検証しているとのことです。企業の立場として、条件設定の違いと成果の違いの関係を特定するなら、詳細な根拠は不明でも大量のサンプルによる検証であれば、確実に成果の向上が期待できるので、目的は達成されるのかもしれません。
ただ、消費者サイドからみると、ネット広告ひとつとっても表示されることが非常に鬱陶しく感じることも少なくありません。デジタル・マーケティングの施策が、消費者側にこうした嫌悪感を与えている側面はあると思います。マーケティング5.0が「人間中心」を標榜するのであれば、「いつ広告表示すれば(嫌悪感を抱かれず)興味を持たれやすいのか」など消費者の状況・心理を見極める必要はあるでしょう。難しい課題とは思いますが、デジタル技術がこうした方向性を見出せるようになることを期待したいと思います。企業にとっても、広告が嫌悪感を喚起するようでは全くの逆効果なので「有効な(興味を持ってもらえる)時と場合」をわきまえることは死活問題とも思えます。顧客経験価値の向上という視点からも重要なテーマでしょう。
DOORS 顧客体験価値の向上を目指して、企業のDX化やビッグデータの活用、収集データの統計処理、パーソナライズやレコメンド機能の実装、それらを自動で的確に行うMAツールなどを用いて、顧客エンゲージメントを高めるための最適なアプローチはなにか。マーケティング4.0以降で重視されてきた社会的価値や精神的価値の提供も含め、このあたりの視点をマーケターとしては持っておく必要がありそうですね。
一方で、データドリブンという言葉も活気づいているという状況もあり、マーケティングがどんどん自動化の方向へと向かっています。機能精度の未熟さ、改良の余地はまだまだ大きいと言えそうですが、これらのマーケティングツールはいかなる機能を実装し、どのように活用することが最良であるとお考えでしょうか?
長島教授 装備すべき機能というより、使い方の問題だと思います。観察眼と洞察力、そして明確な問題意識を備えたマーケターであれば、データ収集機能・分析機能は強力なツールとして役立てることができると思っています。「目的意識」「仮説設定力」の問題と言い換えることもできるでしょう。
いわゆるマーケティングツールは「自動的にうまい方策」を提供してくれる装置と誤解しないほうがよいと思います。ここでもやはり「人間性の問題」ということもできるでしょう。私が20年ぐらい前に企業インタビューを行った際に「データ自体はたくさん蓄積されているが、それをどう活用すべきかがわからない」という声がありました。
DOORS 当時からそのような声があったんですね(笑)
長島教授 はい、そのような企業は当時から多かった印象があります。データ活用の前提として必要になるのが「目的と仮説」です。膨大な量のデータを活用しようと思ったとき、その活用法の組み合わせパターンは、天文学的な数になります。当然、それを一つひとつ点検していくというわけにはいかないでしょう。そうなったときに、マーケターが仮説と目的に即して情報(データ)を活用できれば、つまり「目のつけどころ」が明確であれば、ツールは大きな武器になるはずです。
つまり、使う側の問題意識がしっかりしていることを前提とすれば、ツールは非常に有用だと思います。わかりやすい機能は2つあります。ひとつは「情報提供機能」で、先の例で言えば、見るべきデータや注目すべき関連性、つまり仮説が明確なら、ツールは必要な情報を提供してくれるはずです。
もうひとつは「ソリューション提案機能」です。これは、あくまで「提案」です。しかし、例えば素人が60〜70点を取るために、2〜3年のスキル習得期間が必要であるとした場合、ツールを使うと素人でもすぐに60〜70点が取れる、これは非常に大きな力なのではないでしょうか。
DOORS 面白い視点ですね。
長島教授 また、将来的に熟達者を目指そうと考えた場合に、初期の手間や習得時間を省くために、手始めの導入として使用するのも有効だと思います。ゼロから考える必要はなく、ツールによって「ある程度」考えられたものが提案されてくる。それを軸に、またはその提案をベンチマークとして、自身の知見や能力を付け加えていく、そういった活用の仕方も非常に有効でしょう。または、熟達者のもとで新人の教育ツールとして用いることなども可能かと思います。
わかりやすい機能は2つあると申しましたが、副次的な機能、つまり目に見えにくいのですがツール活用の副産物もあります。こうした副産物の効果のほうが大きい場合もあるでしょう。
現代経営学の考え方「ダイナミック・ケイパビリティ」に即して言えば、センシング(感知すること)やシージング(資源を動員すること)、トランスフォーミング(資源の転換や再配置)というものがありますが、マーケティングツールは、センシングに関して省力化できると思います。
しかし、企業経営ではセンシングに続く実装・変革の部分が重要な意味を持ちます。センシングの負担が大きいと、意思決定や実施に必要な資源が圧迫されますが、センシングの負担が軽減されれば、その後の活動により多くの資源投入が可能となり、結果的に実装・変革の重要性もクローズアップされるでしょう。私はツール活用によるこの効果を「本質抽出機能」と呼んでいます。
もうひとつの副次的機能は「目的確認機能」と命名できるもので、ツールを使うことによって常に問題意識・目的・仮説に立ち返ることができる、というものです。私も大学教員になる以前、30年間一般企業に勤めていましたので経験上よくわかるのですが、日常業務に埋没していると、当初の目的を見失いがちになります。ツール活用は、目的・仮説のリマインダーの役割が期待でき、これは無視できない大きな機能と考えられます。
DOORS 確かに今、おうかがいしたように今後のマーケティング活動には、定量データの収集をもとに、MAツールをはじめとしたテクノロジーの活用を前提とすることは有用だと思います。こうした潮流にある中で、マーケティング5.0と言われる以降の時代に向けて、今後マーケターとしてはどのような視点が不可欠だと思われますか?
長島教授 ツール活用という側面からは「定量データを理解できる」という知識(リテラシー)は必須でしょう。定量データの正確な読み取りを踏まえ、どのような意義を見出すのか。目的が明確なら、データから意味を見出したり、さまざまな可能性を推論したりすることが可能になります。
また、「人間観察力」も重要なキーワードになってくるでしょう。これもマーケターに求められる資質としては昔から変わっていませんが、絶えず観察と思考を続けて仮説を立て、データに基づいて検証していく意志と能力は今後も求められます。さらに付け加えるとするなら、これはどんな職種に関しても共通して言えることですが「マーケターが天職」と思えるほどマーケティングが好きであること。この気持ちがあれば、どんな時代にあっても優れたマーケターとして活躍していけるのではないでしょうか。
DOORS まさに「好きこそものの上手なれ」という言葉通りですね。「これが自分の天職だ」と思えるほどの仕事でなければ「世にこんな価値を提供したい!」という強烈な思いにまでは至らないと思います。少なくとも、マーケターに限らず「こんな風に人々の生活に良いインパクトを与えたい」という社会意識を持っていると、仕事に対して見えてくる視点は大きく変わってくるのではないかと考えます。
長島教授 そうですね。私自身はマーケターではありませんが、私も学生を相手にするときは「社会の中核層になれるような若者たちを育てたい」という気持ちは常に持っていてモチベーションにもなっています。そういった部分はマーケターにも当てはまるのではないかと。人はそのように社会的意義を意識するときに、幸福を感じる脳内のホルモン物質が放出されるという研究結果もあります。利他的な思いを持つ、持つことができるということは、自分自身が幸せなのではないかと思います。
DOORS 長島教授のお話を踏まえて考えると、自分の仕事に対しても”意味的価値”を感じられているかどうかという部分が、いわゆる”いい仕事”を行う上では不可欠なようにも感じました。
長島教授 確かにそうかもしれませんね。私の経験則からも言えることですが、中高年ぐらいの年齢になると多くの人が「つまらない仕事」を何度も経験していると思います(笑)。それが「なぜつまらないのか?」を思い返してみると「仕事がつらいとか大変だ」とかいうこと以上に「仕事の意味や目的に共感できない」という部分が大きいのではないでしょうか。こうした経験からも「自分の仕事に対して意味や目的が持てる」ということは非常に大切なのではないかと思います。
DOORS 自分が向き合っている仕事の意味、考え方に共鳴できるかどうか、これは即ち「自分の仕事に感じている意味的価値」と捉えても差し支えないでしょう。先ほどのMAツールのお話にもあった「目的意識がはっきりしているマーケターにとっては、強力なものになる」というお話とも通じますね。いくらテクノロジーが進化しようとも、大切なのはそのような機械的、定量的な部分以外の、それを用いる人間の情緒や感性、共感力などが重要になっている。これはマーケターでも、他のどの職業でもかかわらず、そういった質的なコンディションを維持したり持っていたりしている人が、この先の時代にも”いい仕事”ができるということなのかと思います。
長島教授 おっしゃる通りだと思います、本当に。質的な面での話に関連する例で思い出すのは「目のつけどころ」の重要さです。かなり古い話になりますが、初期のデジタルツールにPOSシステムがあります。収集されるデータは、購買した人の年齢帯、性別、なにをいつ買ったか――といった基本情報に限られます。
POSデータを見て「商品が売れ残らないように在庫管理や発注を行う」といった考え方もありますが、例えばセブンイレブンのトップを長年務められた鈴木敏文氏は「売上や利益に直結するのは”売れ残り”以上に”機会ロス”である」とおっしゃっていました。
お客様が欲しいと思って来店したけれど、目当ての商品が店頭になかった。このようなケースが、売れ残りよりも売上額へ与えるインパクトは大きいということを、見抜いていました。これもやはり「目のつけどころ」という話かと思います。データを扱う人が、日々の観察と仮説検証の中で培っていくべき力なのだろうと感じます。
DOORS つまるところ、洞察力ということになるのでしょうか。表面的な事象や現象だけの観察、判断ではなく、その背後にある構造を見抜くためには、自分のやっている仕事、意思や意味を”自分自身で理解”していることが大事になってきますね。
長島教授 そうですね。「好きだ」という気持ちを持っていることが前提としては一番だと思いますが、何らかの問題意識を当事者視点で持っているかも重要なポイントになってきます。「やりたいことがある」「変化を起こしたい」といった感情が、視点やセンスにつながる重要な要因になると思います。
ツールの処理能力が向上し、一瞬で膨大な計算ができるようになったからこそ、そこはツールに任せれば気が付いていなかった視点を模索したりすることに人間の能力とリソースを注力できるようになりました。目のつけどころのよいマーケターが、ツールから収集した定量データを的確に把握できれば、まさに「鬼に金棒」でしょう。
DOORS 本日は貴重なお話をいただきありがとうございました。弊社が、企業のデータ分析を支援させていただくビジネスモデルの中で感じる課題として、データ分析を行うにあたっては、多くの情報が氾濫、混乱に陥っているようなケースも多いのだと思います。我々が接するマーケターも、長島教授がおっしゃったように”本質”や”原点”の部分に回帰しようとしているのではないかと感じることが多くあります。ツールはもちろん使うし、データも分析するけれど、決してツール頼みではなく、マーケター自身の視点や思考力の重要性が見直され、あらためて”人間の持つ力”へ立ち返り、テクノロジー活用との両立が大事なのかと感じています。
長島教授 データだけからは読み取れない部分があることは確かです。どこに焦点を当てて分析し、どう次に活かすのか、このあたりは人間の持つ視点や思考力が生み出すものです。その他の計算や処理は機械に任せる。結果として人間は機械やデータからは見えない部分を探っていくことに集中できるようになるということです。
また、過去のデータ分析だけではわからないこと、試行錯誤によって見えてくるものもあるでしょう。組織という側面から、ひとことだけ加えるならば、「やってみてもいいんじゃないか?」といった、試行錯誤を認めるような組織風土を養っていくことも、土台として大切なことなのではないかとつくづく感じています。今日、お話させていただいた内容が、企業にいらっしゃる皆さんにとって少しでもヒントになれば大変光栄です。

