メルマガ登録

こんにちは。エンタープライズユニットの藤本です。
先日のDOORS記事にてご紹介した昭和医科大学との共同研究について、その後の進捗をご報告いたします。現在も継続して取り組んでおり、新たな取り組みを複数行いました。今回はその続報として、学生向けに実施したAIに関する講義の様子や、日本デジタル歯科学会での研究発表についてお伝えいたします。
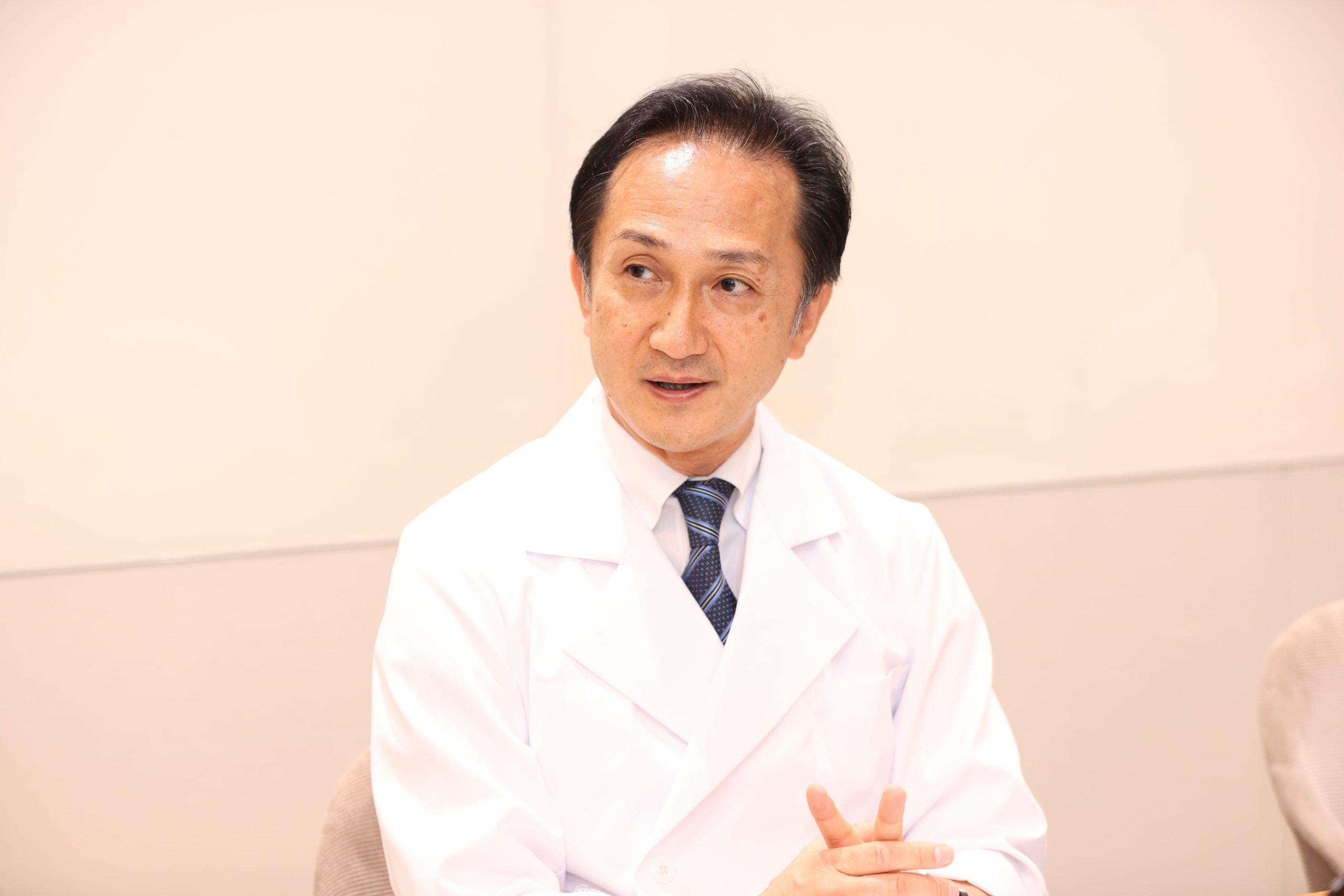
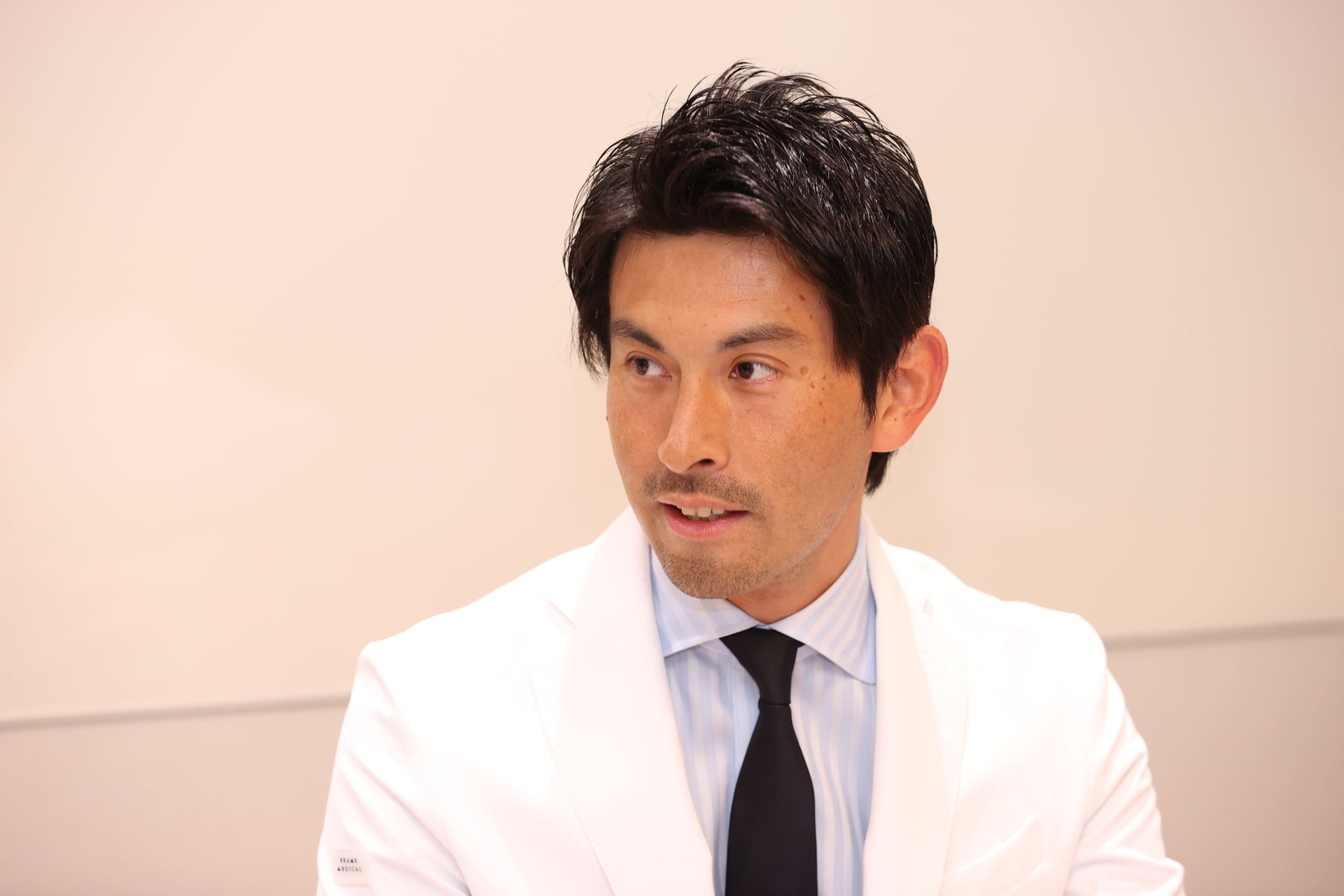




今回の共同研究の延長として、ブレインパッドのメンバー2名が昭和医科大学歯学部の学生向けに、AIに関する講義を実施しました。
「歯学部でなぜAI?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は歯科医療の分野においても、AI技術の理解と活用は重要視され始めています。例えば、文部科学省が定める「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」においても、2023年度からAIに関する項目が新たに盛り込まれ、教育機関としての対応が求められています。
そうした背景を受け、AIやデータ活用の専門家である私たちブレインパッドが、教育パートナーとして講義を担当することになりました。

講義には100名を超える学生が参加し、大学の他の先生方なども聴講に訪れるなど、非常に活気のある会となりました。
講義は大きく分けて3部構成で行いました。
まず、データサイエンティストである私、藤本からは、AIとは何かという基礎知識についてお話ししました。昨今話題になっているAIとはどういうもので、過去から現在に至るまでどのような技術的変遷をたどって発展してきたのかを説明しました。

続いて、弊社執行役員である鵜飼より、民間企業におけるAI活用の実例をご紹介しました。AIはまさに世の中のトレンドであり、民間でも各社こぞってAIの活用に取り組んでいます。さまざまな業種での活用事例を取り上げ、「AIは研究だけでなく、すでに社会の中で実装が進んでいる」という実感を持っていただける内容としました。
特に、若い世代にとって親しみやすいエンタメ分野などを選び、数式や難解な専門用語を避けることで、AIが“身近な技術”だと感じてもらえるよう意識しました。

最後に、私から歯科領域におけるAI・データ活用の現状と今後の可能性についてお話ししました。近年は、口腔内スキャンデータやCT画像、レントゲン写真を用いた画像認識AIの研究が進展しており、診断支援や治療計画の立案といった幅広い分野で活用されています。しかし、AIの精度問題や悪用リスクについても触れることで、単なる技術論に終わらず「医療人としてAIとどう向き合うか」を考えるきっかけとなるよう構成しました。

講義終了後には、複数の学生が登壇者のもとへ個別に質問に訪れました。「さらに詳しく学ぶにはどうすればよいか」「将来、歯科医として開業する際にAIをどう活用していけるのか」といった具体的かつ前向きな声を多数いただき、AIというテーマに対して、自らの将来と結びつけて考えてくれる学生が多かったことに感銘を受けました。
また、受講後に実施した学生アンケートでは、講義内容に対する満足度が非常に高く、「データを活用して様々な問題を解決できることに興味が湧いた」「AIによる医療の効率化に興味がある」といった声が多く寄せられました。特に、歯科とAIの交点に強い関心を示す学生が多く、技術を“自分ごと”として捉えはじめている様子に、未来の歯科医療への明るい期待を感じました。

なお、ブレインパッドでは今回のような大学での講義に加え、高校や専門学校への出張授業やキャリア支援活動など、教育領域におけるAIリテラシーの向上にも力を入れています。下記の記事では、以前行った女子中高生向けの教育プログラムについてご紹介しています。あわせてご覧ください。
【関連記事】
女子中高生 夏の学校 2023 アフタートーク 出会いによって中高生のキャリアの未来が拓ける3日間
これまで共同研究に取り組む中で、昨年12月には画像認識関連の学会「ViEW2024」にて発表を行うなど、研究成果の発信を大切にしてきました。
その発信活動の一環として、2025年5月10日から11日に開催された「日本デジタル歯科学会 第16回学術大会」に参加し、昭和医科大学の先生方とともにポスター発表を行いました。
日本デジタル歯科学会は「国民に対して安全、良質な歯科医療を提供するためのデジタルソリューションの普及」を目的とした学会であり、歯科×デジタルの領域で様々な研究が発表されています。

学会には全国から歯科医師や研究者など、デジタル歯科領域に関わる多くの方々が参加しており、会場内は熱気に包まれていました。
特に印象的だったのは、口腔内スキャナーなど最新のデジタル技術を活用した臨床・研究発表が多く見られたことです。
歯科業界においてもデジタル化が急速に進んでおり、大病院に限らず様々な現場でデジタル技術を活用し、診療に取り組んでいることがわかりました。そういった世の中の流れを肌で感じ取ることができ、改めて学会に参加する意義を感じました。
私たちが学会で発表した研究テーマは「深層学習を用いた不正咬合分類モデルによる診断サポートの実現可能性検証」です。これまでは不正咬合(歯の噛み合わせの異常)の評価において、歯科医の視診と経験が大きな役割を担ってきました。ここにAI技術を用いることで、より定量的かつ安定した判別が可能になるのではないかと考え、進めてきた研究です。

本研究では、6つの画角から撮影した口腔内写真を元に、不正咬合を判別する画像認識モデルを構築し、8種類の不正咬合をどのくらいの精度で判別できるかを検証しました。
モデルには事前学習済みの画像認識モデルである「EfficientNet」を使用し、昭和医科大学の先生方に集めていただいた約1,000名分の口腔内写真データを使ってファインチューニングを行っていました。
現時点の成果として、一部の判別しやすい不正咬合(開咬など)はAUCで0.9以上と比較的高い精度で判別できています。一方で、判別が難しい不正咬合(正中離開など)はAUCが0.7前後と、依然として課題が残ります。シンプルなファインチューニングで高い精度を出すことのできるAIの優秀さを感じつつも、歯科医の先生方が判断に悩むような症例はやはり精度の壁に直面しています。今後は、さらなる研究を通じてこの課題を解決していきたいと考えています。
ありがたいことに、この研究成果が高く評価され、最優秀発表賞を受賞することができました。表彰式兼懇親会の場では、多くの先生方からお祝いの言葉をかけていただきました。
数多くの素晴らしい研究がある中でこのような賞をいただき、大変嬉しく思います。これを励みに、さらに研究を発展させていきたいという思いを強くしました。

ブレインパッドでは、AIを活用したビジネス支援にとどまらず、大学や研究機関との連携を通じて、医療・教育といった公共性の高い領域にも貢献することを目指しています。
今回の講義のように、次世代の歯科医師や研究者にAIリテラシーを広めていく取り組みも、継続的に実施していきたいと考えています。AIが医療に与える影響は大きく、その可能性を現場の方々に伝え、活用していただくためには、こうした地道な教育活動も不可欠です。
私たちは今後も、産学連携の形でさまざまなプロジェクトを推進していきたいと考えています。
最後までご覧いただきありがとうございました。共同研究や教育活動に関するご質問がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
あなたにオススメの記事

2023.12.01
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24
【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08
DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23
LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22
生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説

