メルマガ登録
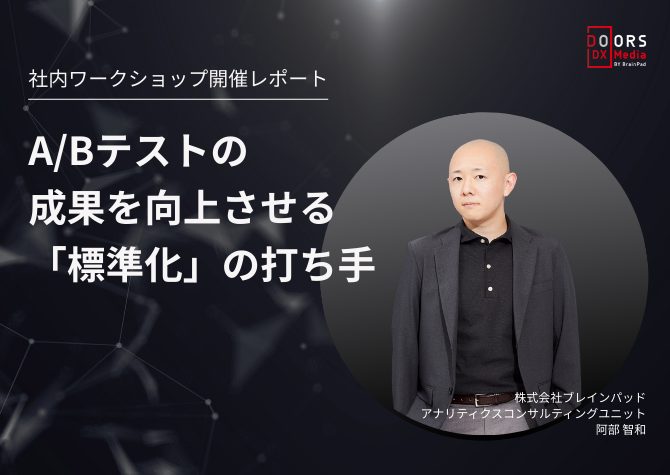
二種類のパターンを比較することで施策の意思決定を行うA/Bテストは、マーケティングやプロダクト改善といったビジネスの現場において、データドリブンのゴールドスタンダードとなっています。その枠組みはシンプルが故に奥が深く、一見簡単にできてしまうからこそ気づかぬうちに落とし穴にハマっていることが少なくありません。
ブレインパッドでも様々な企業様のA/Bテストを支援してきました。A/Bテストのやりこみ度や扱う施策によって直面する課題は違えど、共通する勘所が存在するのもまた事実です。
そこでこのたび、成功事例を結集する場として社内ワークショップを開催しました。ブレインパッドのデータサイエンティストの中でも選りすぐりのA/Bテストプレイヤーを募り、「A/Bテストの標準化」というテーマを設定し、PDCAを通して成果を上げる仕組みづくりの課題と打ち手を議論しました。

本記事ではワークショップを通して見えてきたA/Bテストの課題と、課題を乗り越えて標準化へとたどり着くための糸口をお伝えしつつ,ブレインパッドのデータサイエンティストがA/Bテストに関して行っている取り組みのご紹介をいたします。
本稿で扱う課題と打ち手に関しては組織の状況、A/Bテストの活用度を問わず共通する点を取り上げております。分析サイドにも施策サイドにもお読みいただけますと幸いです。
そもそもなぜ「標準化」に焦点をあてたのでしょうか。
それは「標準化」が、A/Bテストを通した意思決定プロセスを効率的に、かつサイエンス視点で信頼できる結果にもとづいて実行するために重要なステップであるためです。「標準化」されていない状態、すなわち指標の選び方や分析のやり方が組織内でバラバラな状態では、設計や分析の工数が嵩むだけでなく、統計的に誤った判断を下してしまうリスクも高くなります。ひいてはA/Bテスト自体のコストがかかるばかりで改善がすすまない、という本末転倒な事態にもなりかねません。
「標準化」はそうしたリスクを回避し、組織として効率よく成果を上げていくための土台作りと言えるでしょう。特に「標準化」がその価値を発揮するのは、A/Bテストの実行回数が増え、A/Bテストを通した施策判断・改善が普及してきた組織においてです。データドリブンな土壌が耕されたタイミングだからこそ、ビジネス視点でもサイエンス視点でもよりよいA/Bテストのありかたを根付かせていく必要があります。
ワークショップでは、A/Bテストの現場で生じている課題をかき集め、分類していく作業を行いました。課題を洗い出すにあたっては以下の2種類のフレームワークを用いています。
ひとつはいわゆる「PDCA」型の分類です。施策のプロセスに沿って考えることで、実務の場面に照らし合わせた具体的な課題を見つけやすい分け方です。ふたつ目は課題の背景による分類として「組織・文化」「スキル・リテラシー」「ツール・データ」の3つの軸で考え、どの程度コントローラブルか、課題を解消するためにどういったアプローチが有効か見極めるためにも役立ちます。
ワークでは課題を洗い出したのち、その背景を考察、課題を解消するための打ち手を整理していきました。この記事では課題と打ち手の中でも特に意見の多かった「組織・文化」に関する課題と打ち手をピックアップしてお伝えいたします。施策のPDCAサイクルに始まりKPIマネジメント等ビジネス側の上流工程に携わる中で見えてきたものと言えるでしょう。
分析を担うチームと、施策立案・実行を担うチーム(PdMやマーケティング部署を想定)の連携に課題があるケースです。例えば以下のような状況があてはまります。
短期的に見れば「施策をリリースしたい」施策チームと「正しい分析をしたい」分析チームでは追いかけているものが異なるため、こうしたディスコミュニケーションは起こりうることと思われます。しかし、それぞれの背景にある「効果がある施策をリリースし、売上を向上させたい・サービスを成長させたい」という思いは共通のはずです。
ひとつの打ち手として挙げられたのが、分析チームがA/Bテストの重要性を施策チームに伝える機会を設けるというものです。定例や施策に関する打合せとは別に、ふたつのチームに共通の目的は何なのか、そのために分析チームとして何ができるのかといった整理を行い、A/Bテストの価値を再定義します。ブレインパッドとしても、こういった話し合いを通じてより施策チームへの報告クオリティを高めたり、分析業務が円滑になった事例が複数存在しています。
このとき重要なのは、分析チームが分析の精度や統計手法を主語とするのではなく、施策チームのミッションに沿った伝え方をすることでしょう。A/Bテストによる判断を誤った場合にどのくらいの損失が生じ、テストによってどのくらい回避できるのかといった要素を試算し、お互いの文脈を合わせることでコミュニケーションが一歩前進します。
分析チームと施策チーム・意思決定者との目線合わせといった要素は過去の記事でも解説されております。ぜひ併せてご覧ください。
A/Bテストを実行する際には以下のような問いに答えねばなりません。
これにはビジネスとデータサイエンスを横断した理解が求められ、施策・分析両チームのスキルが必要です。しかし、プロセス全体を通して関わる人数を増やせば両者の工数を圧迫するだけでなく、施策のリリースに時間を要し、結果的に生産性を低下させてしまいかねません。
対する打ち手として、A/Bテストの各プロセスを型化・テンプレート化し、工程の標準化・効率化を図る取り組みが有効となります。例えばA/Bテスト設計の手順書・穴埋めテンプレートを作成したり、分析プログラムを型化することで観点の抜け漏れやロジックのミスが減り、標準化に大きく貢献します。
テンプレート化に際しては、全体をリードする役割を設けることが重要です。施策・分析だけでなくエンジニアやデザイナーも含めたプロセスを描くため、組織間を横断して合意形成を行う必要があるでしょう。
またワークショップでは、施策結果のナレッジをどのように蓄積・活用していくかも話題となりました。この点については、決まった形式(テンプレート)を作成して効率化する案や、生成AIを活用してナレッジを収集する案が出されました。
A/Bテストが普及し、当たり前のように実行されるようになった文化でもなお気をつけるべきポイントがあります。「A/Bテストのおかげでよい施策の選択ができる」という言説が独り歩きしてしまい、いわばA/Bテストの実施が施策リリースの免罪符となっている状態です。
大きく二通りの背景があると推察されます。
まずひとつ目に、施策をリリースすることが前提となっており、信頼性が劣後するケースです。A/Bテストを行うことでより確からしい選択ができるのは、一定の信頼性が確保された状態で意思決定を行う場合です。しかし設計が疎かになったり結果から都合の良い解釈をしてしまっては、上げられたはずの成果を失うリスクがあります。A/Bテストを行う目的を見直す必要があるでしょう。
ディスコミュニケーションの課題と類似する打ち手となりますが、望ましくない選択をとった場合の損失をシミュレーションし、信頼のおけるテストの実行と判断を定着させるコミュニケーションをとることとなります。
一方で、A/Bテストという取り組みを信頼するあまり、あらゆる変更をA/Bテストに任せているケースも考えられます。この場合、A/Bテスト自体に発生するコストが過剰になっていないか気を付ける必要があります。サンプルサイズが潤沢でテストがほぼ自動化されている場合はともかく、実際にはテストをすることによる機会損失があり、また人的コストもかかっている場合が多いのではないでしょうか。
本記事の主旨とは逆説的に聞こえますが、A/Bテストをせず、信念に則って施策をリリースするという選択肢も存在します。これは、A/Bテストを通した意思決定の質の向上で得られるリターンが、A/Bテストの取り組みそのものにかかるコストを下回っているような場合が該当します。
具体的には以下のようなシチュエーションが想定されます
一度立ち止まり、A/Bテストの価値がどこにあるのか、それが本当に求められている場面なのかを考えることも分析チームに求められている役割です。
※施策により売上やユーザ体験が大きく損なわれないかを確かめる分析や、施策の改善を目的とした種々の分析は有効でしょう。
A/Bテストを通して成果創出のサイクルを回していくには「標準化」が重要だという立場のもと、ワークショップを通して整理された「標準化」を阻む課題とその打ち手を挙げてきました。
共通しているのは単に分析技術による解決が可能な課題ではなく、関係者を巻き込み組織のコミュニケーションや考え方を変えていく、地道な活動を必要とするという点でしょう。
A/Bテストは技術の研究が進み、国内外に豊富な先進事例もある中、現場で実行するには様々なハードルがあることも事実です。情報を集め理想を見据えつつ、足元の一歩を着実に進んだ先にこそ成果が生まれます。
この記事がベストプラクティスを求める皆様のお役に立てれば幸いです。
あなたにオススメの記事

2023.12.01
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24
【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08
DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23
LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22
生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説

