メルマガ登録
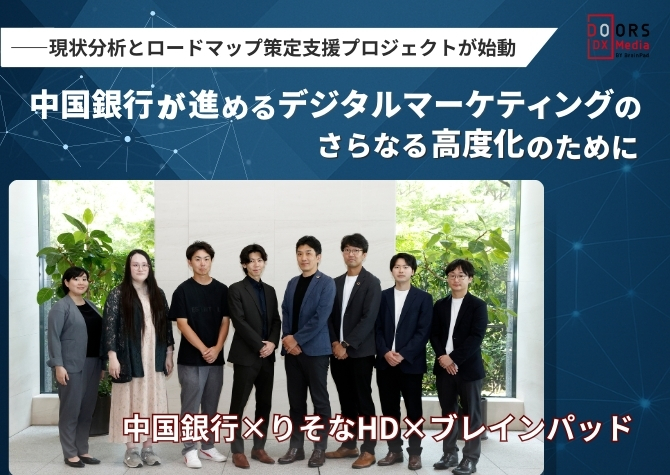
中国銀行では、2021年頃からデジタルマーケティングのチームを組成し、人員も増強しながら手探りでデジタルチャネルの拡充とデータ利活用に取り組んできました。この取り組みをさらに高度化させ、次のステップへと進む計画立案のために、2025年4月からの3か月間、実施されたのが「マーケティングアセスメント支援」プロジェクトです。
地銀業界をリードするOne to Oneマーケティングの実現に向けた中国銀行の取り組みを、株式会社りそなホールディングス(以下、りそな)と株式会社ブレインパッドが伴走者となって 支援する本 プロジェクト。3社のメンバーの方々に、プロジェクト立ち上げの背景やアプローチ、今後の方向性などについてお話を伺いました。
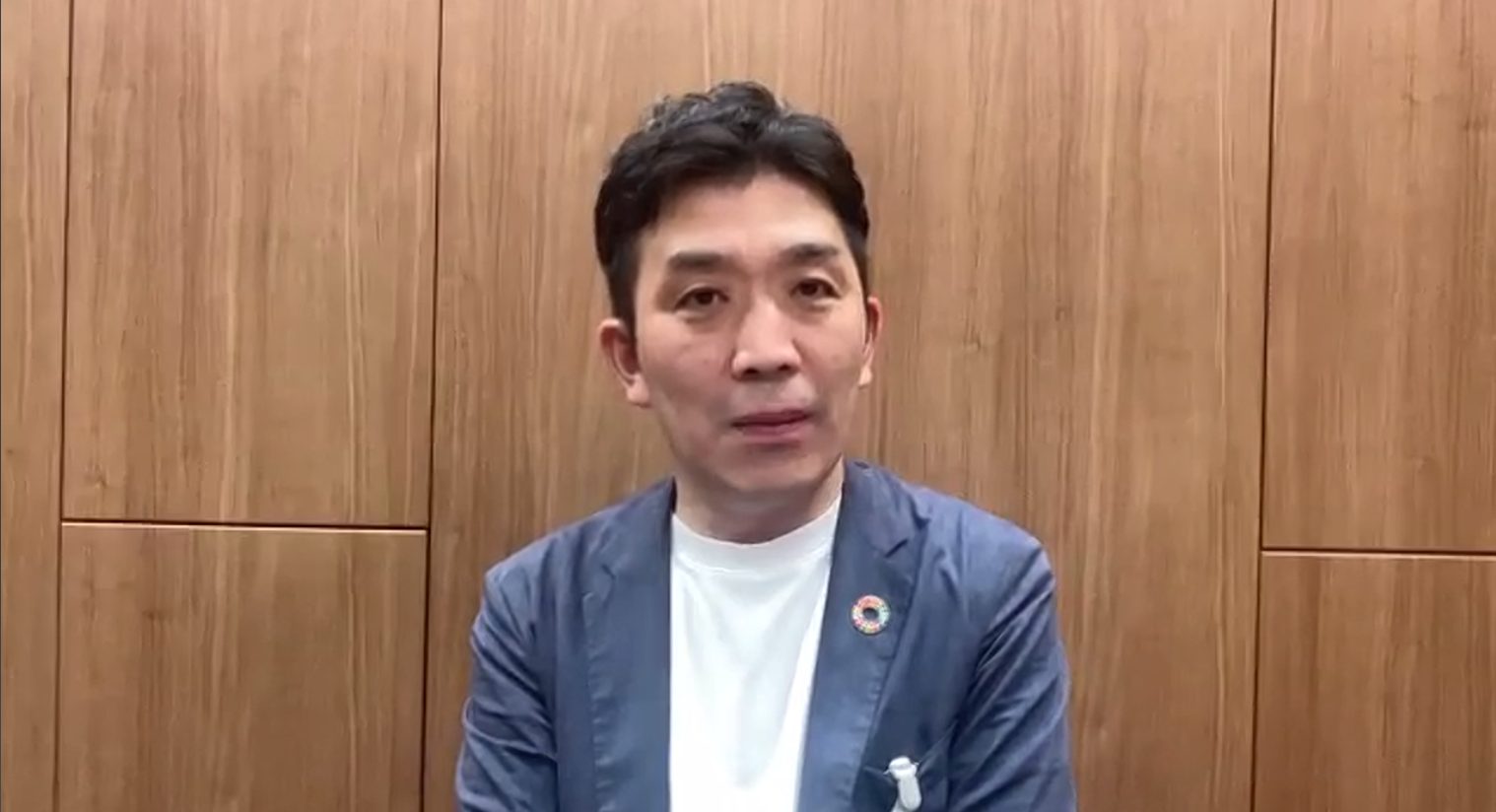
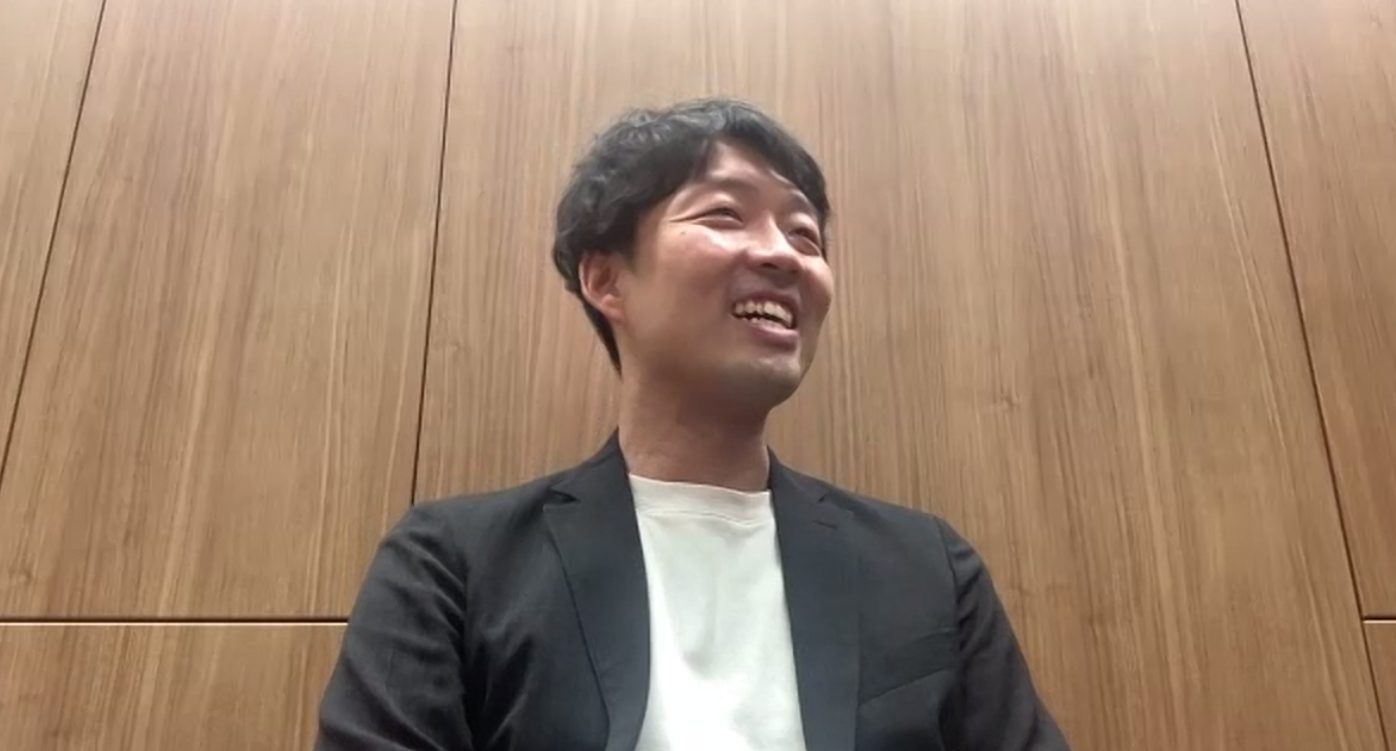
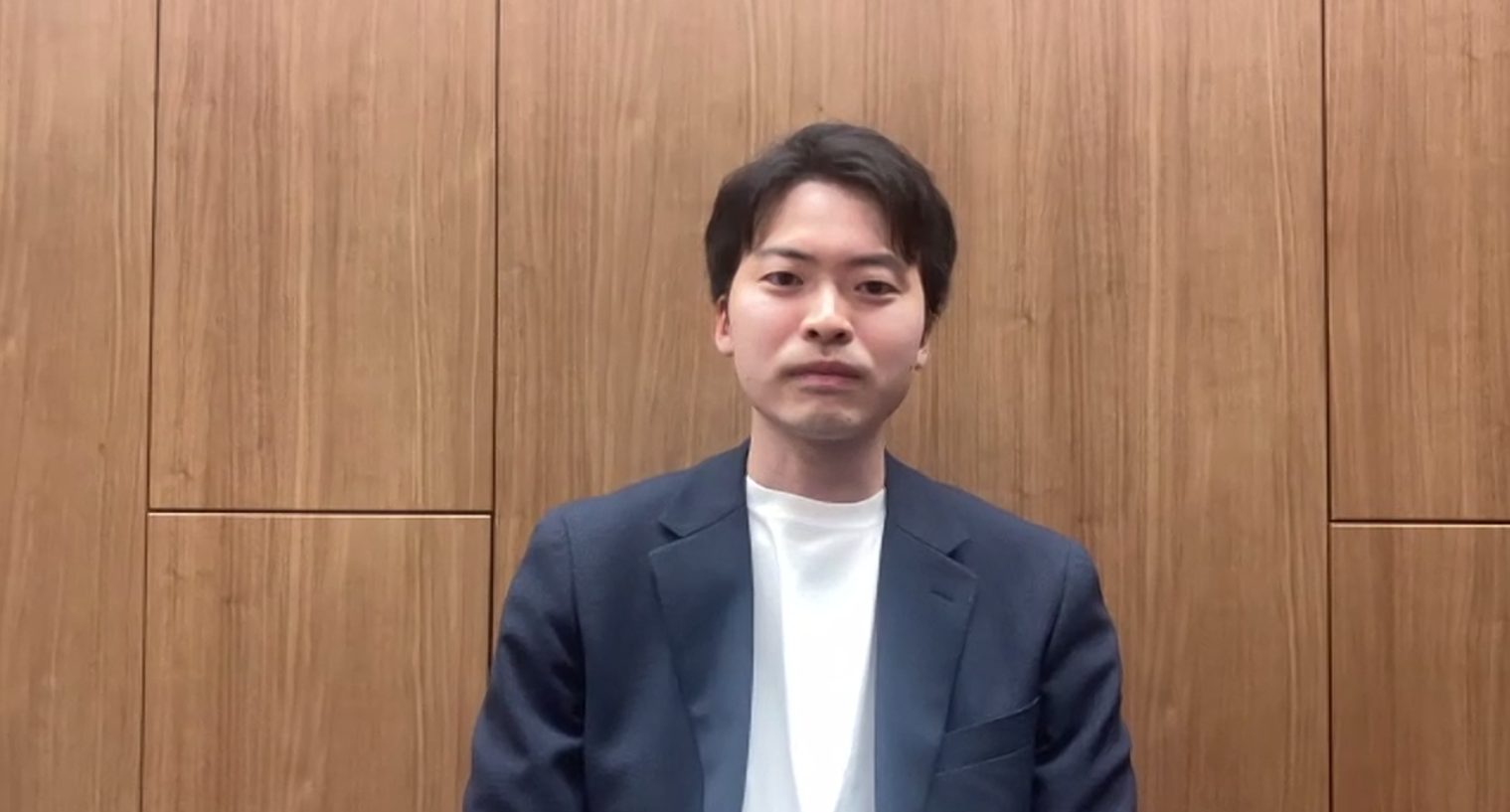
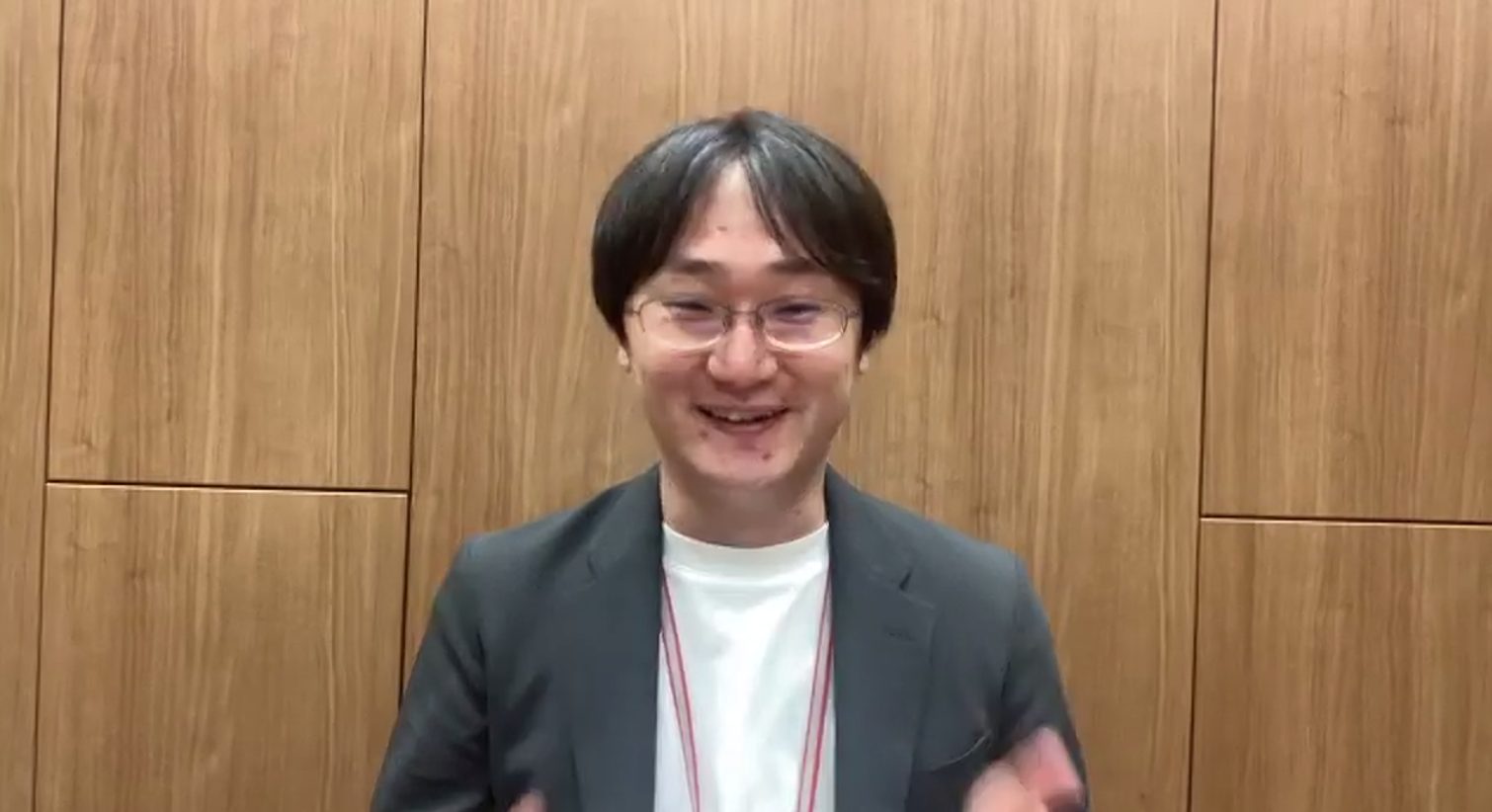

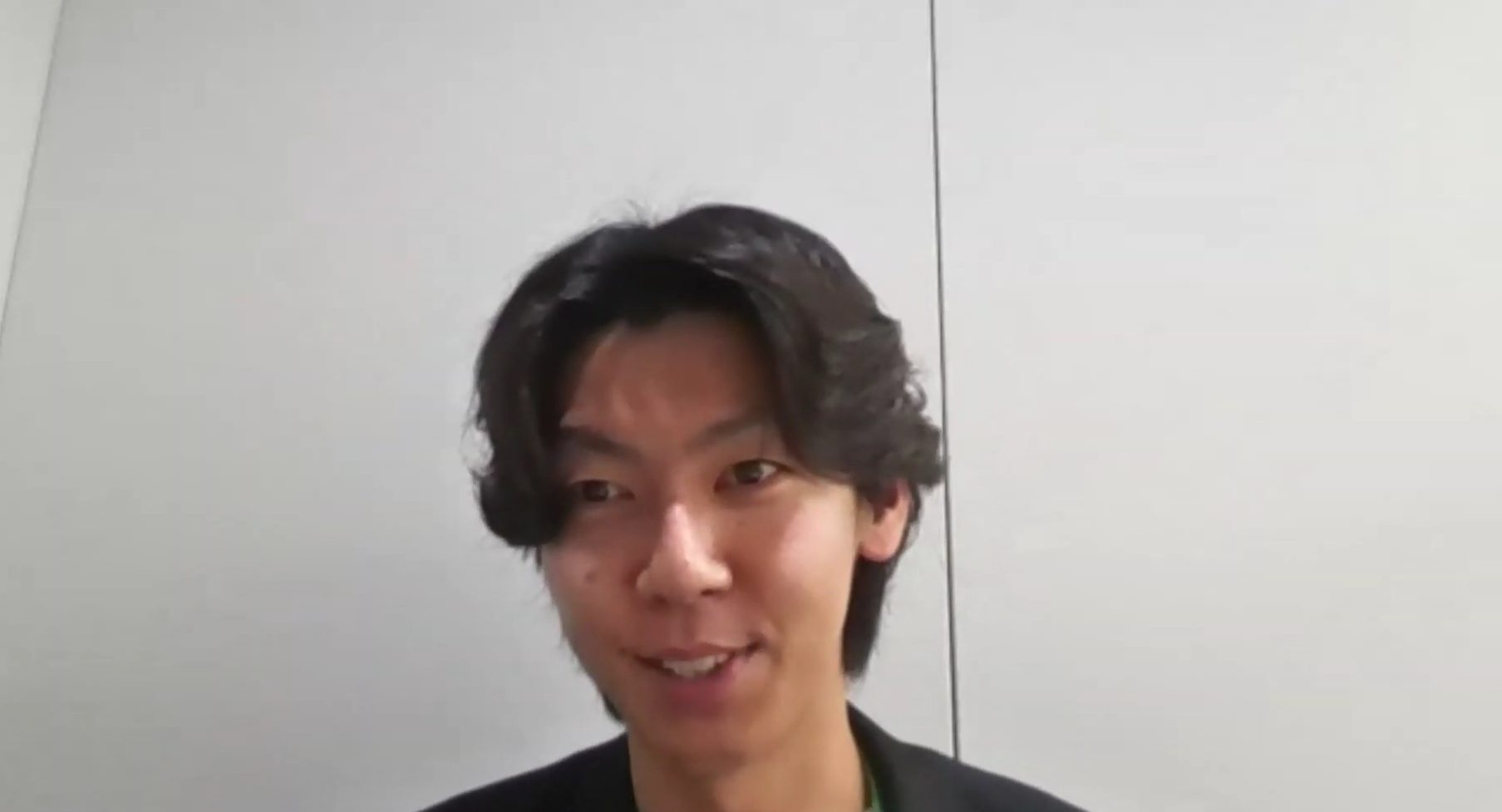


DOORS編集部(以下、DOORS) まず、プロジェクトの概要を本案件のプロジェクトマネージャーのブレインパッド・加藤さんから説明していただけますか。
株式会社ブレインパッド・加藤ゆき音(以下、BP/加藤) 背景として中国銀行さまではこの数年、デジタルマーケティング業務におけるデジタルチャネルの整備とデータの利活用に取り組まれてきました。
銀行アプリや法人向けポータルサイトといったデジタルチャネルの強化に加え、各チャネルで接点を持てる顧客数を増やし、新しいCRMの導入も見据えた準備を進めています。こうした状況を背景に必要となったのが、デジタルとリアルを融合させたOne to Oneマーケティングをさらに高度化するための計画です。
中国銀行さまの取り組みを次のステップへと進めるために、現状分析とロードマップ策定支援を実施する本プロジェクトを立ち上げました。

DOORS 中国銀行さまがデジタルマーケティングに取り組み始めた経緯について教えてください。
中国銀行・小野敬広氏(以下、中国銀行/小野氏) 従来は営業店の窓口や営業担当が対面でお客さまに営業するという形態が当たり前でしたが、対面でお話できているお客さまは全体のわずか 10%ほどという状況でした。 普段お会いできないお客さまにも中国銀行と取引して良かったと思っていただける付加価値を提供 するために、中国銀行では4年ほど前からデジタルチャネルの強化に向けた取り組みを開始しました。
当初のデジタルチャネルで行える施策はメール送信ぐらいだったのですが、お客さまごとの情報の出し分け、ATM画面でのお客さまに合ったコマーシャルの表示、銀行アプリやホームページ上でお客さまに適したバナーを出すといった施策を実施してきました。こうした施策は特に外部からの助言、支援を受けたわけではなかったので、果たして適切なのかという疑問を抱いたこともあります。
さらなる高度化のためには、専門的な知識を持つ第三者から の 評価 が必要だと考えました。ロードマップを描き、どういった状態を目指すのか、何をすべきかを整理するために、今回ブレインパッドさまとりそなさまにご支援を依頼しました。
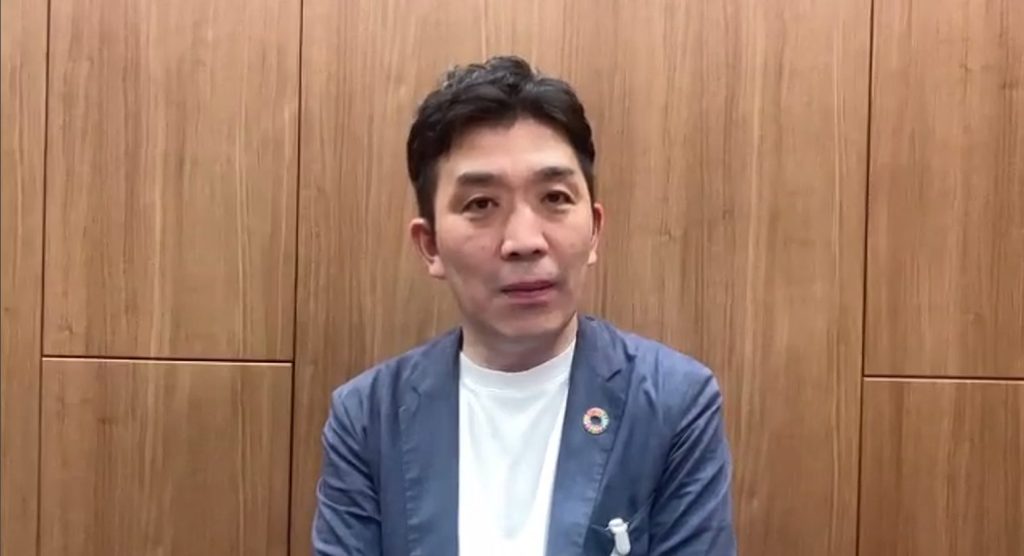
DOORS りそなさまが今回のプロジェクトに参画した経緯はどのようなものでしょうか。
りそなホールディングス・扇田賢氏(以下、りそな/扇田氏) 僭越なお話ですが、弊社が2018年にリリースしたバンキングアプリが対外的に高く評価されていると認識しています。
DX銘柄に選ばれるなど外部から評価いただいたこともあり、地域金融機関さまからベンチマークにしていただくことが非常に多いのです。そうした評価を得ていることが、このプロジェクトに参加させていただいた理由だと思っています。
今回、中国銀行さまが現状を整理しデジタルマーケティングに関する戦略を立案するというお話でしたので、私どものデータ利活用における成功事例だけでなく、失敗事例も共有させていただき、最短距離で立案できる形に持っていければと考えました。
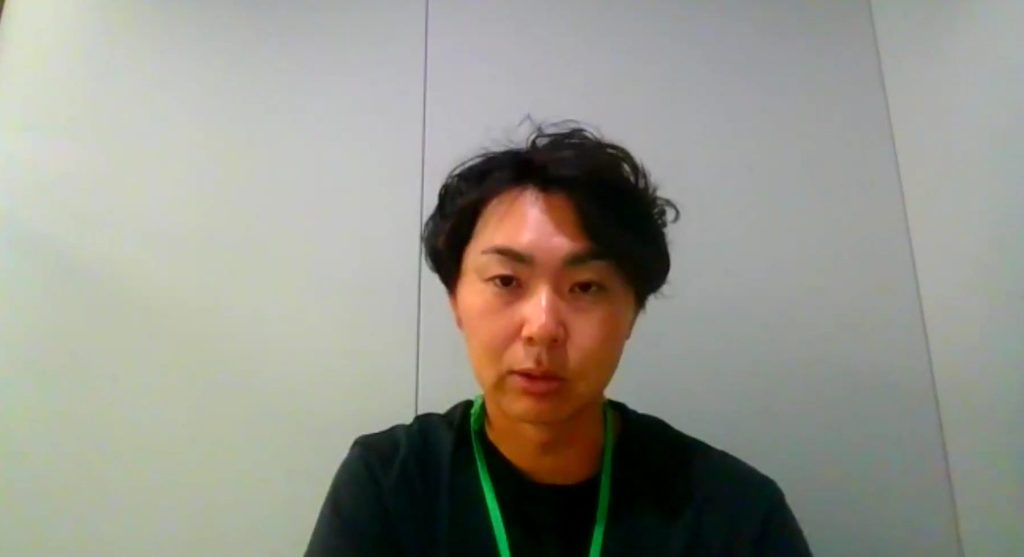
DOORS このプロジェクトにおけるブレインパッドの関わり方の基本姿勢を聞かせてください。
BP/加藤 データを使って何かをしたい方々、特にデータはあるがビジネスのサクセスにつながる活用方法を知りたい方々への支援が、弊社のいちばんの得意領域です。
中でも、マーケティングに関する支援実績が豊富で、期待される領域であるほか、 金融機関を専門とするユニットも有しています。中国銀行さまからご依頼いただいた内容は、まさに弊社の強みが掛け合わさった部分ではないかと考え、お話を進めさせていただきました。
りそなさまといっしょに体制に入って地域金融機関をご支援させていただく案件もこの数年、複数実践しています。データとマーケティングのプロであるブレインパッドと、銀行としてのアドバイザーのりそなさまという座組によるご支援は、中国銀行さまに大きなバリューを提供できると考えました。
【関連記事】
百十四銀行×りそなHD×ブレインパッド。「地銀DX」の裏側と、3社のパートナリングがもたらす地域経済活性化
DOORS これまでの中国銀行さまの取り組みでは、どのようなことを実践して、どのような成果や課題が生じたのでしょうか。
中国銀行・松田稔弘氏(以下、中国銀行/松田氏) 中国銀行では、徐々にマーケティングチームのメンバーを拡充して、データ活用やデジタルチャネルでの情報提供のための体制作りを外部に頼らずに進めてきました。
自社だけで取り組んできた理由は、主に2点あります。まず初期段階では、チャネルの整理など、ある程度ミッションが明確だったこと。もうひとつの理由は、いきなり外部から知見をいただいて、出来上がったものをスキルトランスファーしたとしても、行内にすぐに蓄積できないと考えたからです。試行錯誤しながらステップを踏むことで、行内に経験やナレッジを蓄積していくことを重視してきました。戦略や施策、組織体制といった部分も、これまでは行内で独自に考えてきた部分が多分にあります。トライアンドエラーを繰り返しながら、やるべき部分を実現してきたという認識です。
デジタルマーケティングの領域をさらに高度化していくにあたって、これまでの行内の取り組みに対して第三者からの評価が必要となり、外部の専門的な組織からサポートを受ける最適なタイミングが訪れたと考えました。その第三者としてブレインパッドさまとりそなさまに本件に参画していただき、単なるアドバイザーではなく伴走者としての役割を担っていただきました。
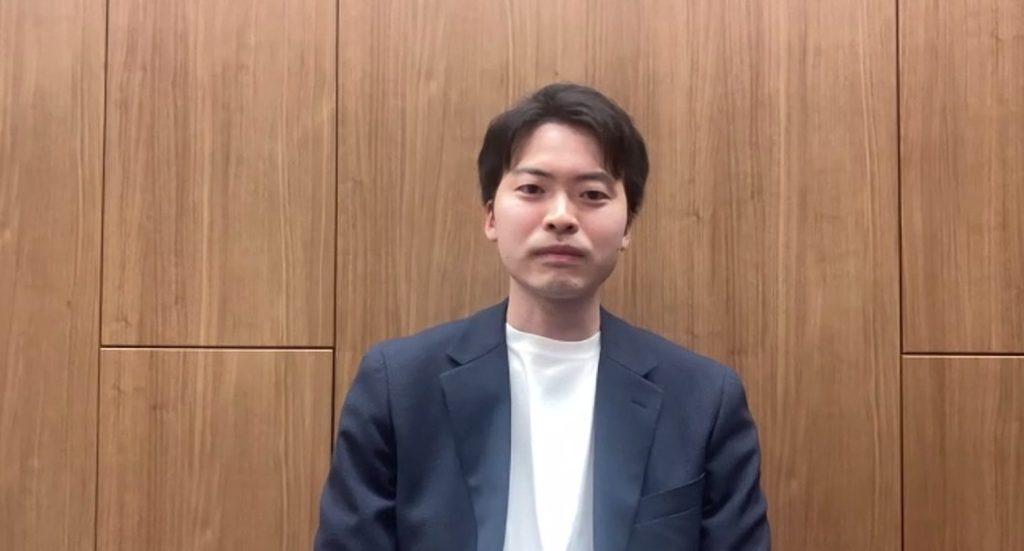
DOORS そうした中国銀行さまのフェーズに即して、ブレインパッド、りそなさまはどういった方法で伴走者としての役割を果たした のでしょうか。
BP/加藤 我々はマーケティング組織を診断するフレームワークを持っています。そのフレームワーク上の評価観点を用いて、どういった商品チームの方々がどのような思いでマーケティングの戦略立案や施策の実行をしているのかといった部分を評価していきました。
ヒアリングと提供していただいた資料を通して、実態を把握します。これを我々はアセスメントと呼んでいるのですが、まずは施策や体制、データ利活用の現状などに関するファクトを収集します。
そのうえで、我々が考える「目指す姿」や、りそなさまの事例とのギャップを明らかにし、中国銀行さまの現状とこれからの進め方をご提案し、ロードマップの形にしました。ロードマップでは、直近優先して取り組む 領域についても、具体的に提言しています。
りそなホールディングス・長谷川颯氏(以下、りそな/長谷川氏) ロードマップを策定するにあたり、最短距離を進んでいただきたく、組織の立ち上げ時や成長期、現在のりそなと中国銀行さまを比較させていただきました。中国銀行さまのほうが進んでいる部分もございますし、りそなのほうが進んでいるだろうという部分もございます。
同じような悩みを抱えている点については、我々がどういうプロセスを経てきたかをお伝えすることで、よりスムーズな戦略立案に貢献できたと考えております。
例を挙げると、マーケティングにおいては個別商品の訴求に偏りがちですが、バンキングアプリのリリースにあたって、そこを見直しました。お客さまのエンゲージメント向上を目指し、データに基づいてパーソナライズ されたご案内をすることで、お客さまへの価値提供を強化する流れに変えていきました。現在はエンゲージメント向上を目的とした情報提供の割合が半分以上となっています。
そうした取り組みを中国銀行さまにしっかりお伝えすることで、我々のナレッジや経験を活かしていただければと考えております。
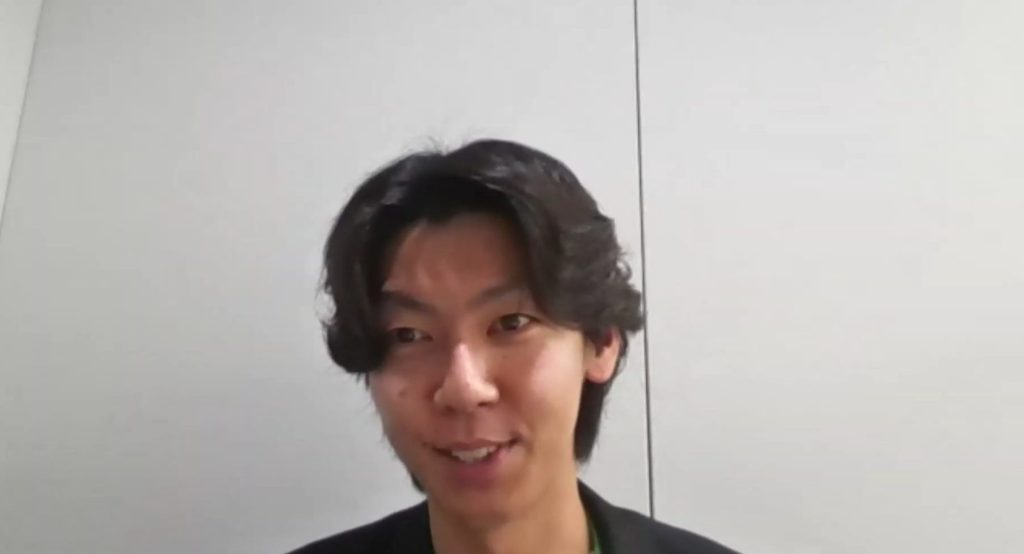
【関連記事】
【前編】静岡銀行のデータ利活用高度化の取り組み-「ビジネスに始まり、ビジネスに終わる」を、「あるべき姿」より「目指すべき姿」を徹底
【後編】静岡銀行のデータ利活用高度化の取り組み-「ビジネスに始まり、ビジネスに終わる」を、「あるべき姿」より「目指すべき姿」を徹底
DOORS このプロジェクトの具体的な進め方と進捗状況を説明していただけますか。
株式会社ブレインパッド・小川茉莉(以下、BP/小川) このプロジェクトでは、まず、中国銀行さまの中で23件、50名以上の方にヒアリングをさせていただきました。マーケティングチームの方々だけでなく、他部署や役員の方々も含めて、さまざまな立場の方々にお話を伺い、中国銀行の皆さまに納得してもらえるロードマップの作成を心掛けました。
ヒアリングで得た情報やご提供いただいた資料を、我々の持っているフレームと照らし合わせながら評価し、その評価に基づいて策定したのが、3か年のロードマップです。
今後は、特に戦略構築、それに施策実行のPDCAを回していくことを重視して、中国銀行さまに高度な施策へのチャレンジをしていただく段階になります。
プロジェクトの実施過程で 、中国銀行の皆さまが感じたことや印象に残っているインプット、エピソードなどがあれば、ぜひ伺いたいです。

中国銀行/小野氏 加藤さんと小川さんのお人柄なのでしょうか、当初から各セクションとスムーズに接点を持っていただき、ヒアリングで深く聞き出していただいたと思っています。
中国銀行・田尾裕一氏(以下、中国銀行/田尾氏) これまで取り組んできたことが頭の中に知識としてストックはされていたのですが、構造化して報告書などに落とし込んでいただいたことで整理できました。上層部や他部署へ説明がしやすくなり、構造化の重要性を強く感じました。たいへん感謝しています。
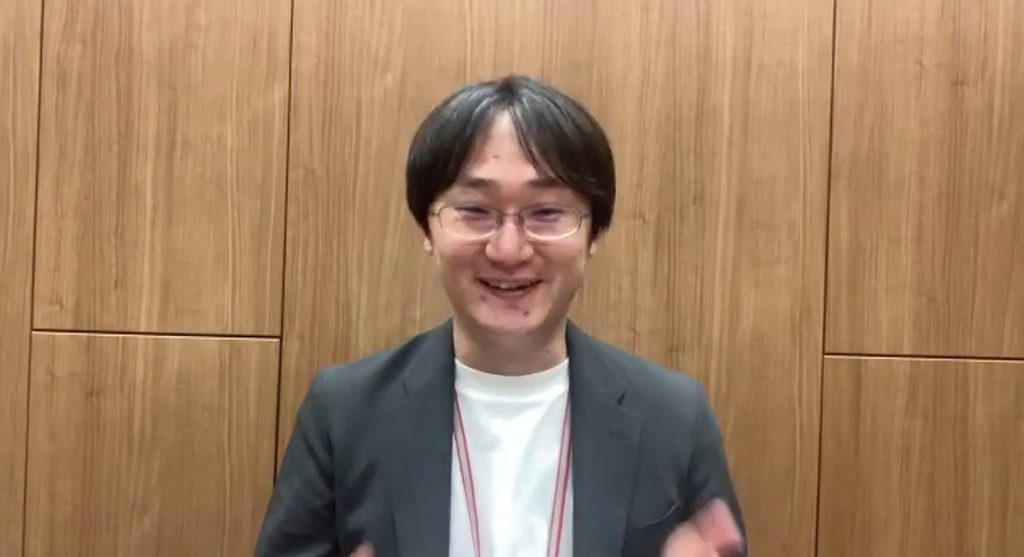
BP/加藤 ヒアリングでは、さまざまな部署の方々にお話を伺うので、デジタル・リテール営業部はこんなことをやっているんだということをアピールする機会にもなればと思っています。
こういうことをデジタル・リテール営業部がやりたいと思っていて、外部のコンサルもそれを後押ししているということを社内全体に浸透させる良い機会になったと思っています。そういった動きになるように、本当は私は穏やかで控えめなキャラクターなのですが(笑)、あえて冗談を交えて場を盛り上げるなど、パフォーマンスを乗せる努力もしました。
中国銀行/小野氏 そんなご苦労があったとは(笑)。加藤さんがおっしゃる通りで、我々が働きかけても、重要性は理解はするけど忙しいからといった反応が返って来ることも少なくありません。ブレインパッドさまは聞くだけでなく、多くの情報も与えてくださり、社内で募った質問にもお答えいただいたので、多くの刺激がありました。データの重要性やこのプロジェクトの大切さが伝わったと思います。
中国銀行/松田氏 私はほぼすべてのヒアリングに参加させていただきました。マーケティングの高度化という観点では、関係者の意見を聞けて非常に良かったと思います。
DOORS ヒアリングでブレインパッドが得た感触、意外だった点などについて聞かせていただけますか。
BP/加藤 中国銀行さまが我々に期待して、多くの方々を巻き込んでセッティングしてくださったのが、心強かったですね。
ヒアリングの感想としては、データ活用に期待されている、望まれている方々が多いわけではないのですが、こういう部分にはデータを用いた方が良いといったご意見を伺うことができました。
ロードマップという形で計画を策定する際に、絵空事ではない本当にやりたいものにできたと思っています。そうした実効性のあるロードマップ作りに、ヒアリングで生の声を聞かせていただいたことが大いに役立ちました。多くのご意見をお伺いできて本当に良かったというのが、率直な感想ですね。
BP/小川 ヒアリングと資料提供を通じて調査を進める中で、1年間のマーケティング計画のような形式的な資料は必ずしも整備されていませんでした。しかしヒアリングからは、自分たちのマーケティングをどう発展させるかについて深く考えられていることが分かりました。マーケティングチームの方々は「理想の組織像」や「One to Oneマーケティングの将来像 」をそれぞれ描いており、それを明文化して戦略に落とし込むプロセスを次のフェーズで進められると考えています。
BP/加藤 ヒアリングに限らず、ご支援全般を通じて感じたのは、中国銀行の皆さまはたいへん謙虚でいらっしゃるんですね。実は非常に高度なこと、チャレンジングなことをされているんですが、すごいことをやっているよという感じではあまりおっしゃらない方々が多いんです。ヒアリングの場が「(普段なら話さないが)求められたので話そう」という動機付けになって、さまざまなお話をお伺いできたのかなと思っています。今後、高度化をするための土台となる環境、人財、スキルを皆さまがお持ちであることは、最終報告の中でも述べさせていただきました。
DOORS りそなさまのお立場で、実際にプロジェクトが始まってから認識された点などはございますか。
りそな/長谷川氏 りそなは今回のプロジェクトで、中国銀行さまからデータ利活用や人財育成、組織に至るまで幅広いご質問を頂戴し、我々の成功や失敗を踏まえてナレッジをお伝えしました。
リモートでのやり取りをメインとした支援でございましたため、コミュニケーションのハードルが高い面がございましたが、しっかり伝えるべきところはお伝えできたと考えております。
DOORS 中国銀行さまが考えているこのプロジェクトのゴール、ロードマップで重視している点についてお聞かせいただけますか。
中国銀行/小野氏 銀行全体の営業力を上げていくために、データ活用やデジタルマーケティングが社内に浸透し、しっかり回っていく仕組みを構築することが、このプロジェクトのゴールです。そのためには今、我々が取り組んでいる部分を拡大して、他のセクションも巻き込みながら展開していく必要があると思っています。
今回のロードマップでもご提言いただいた通り、商品をどう売っていくのかに考えが行きがちなのですが、そうではなくて、ロイヤルカスタマーのようなお客さまを増やす顧客志向の施策も 実践していくべきだと考えています。
BP/小川 ゴールに関しては、皆さまそれぞれにビジョンをお持ちだと思うのですが、いかがでしょうか。
中国銀行/田尾氏 データやマーケティングについて行内外の方々から相談や質問をされるような存在になりたいと思っています。専門スキルを活かして、中国銀行の価値向上に取り組んでいきたいと考えています。
中国銀行/奥川氏 私がデジタル・リテール営業部に着任したのは約1年前です。それまでは営業店で主に法人向けの営業活動をしておりました。着任した当初は、右も左もわからないようなところから始まりました。
今回のプロジェクトを通じて、部署のミッション、マーケティングやデータ利活用の重要性を改めて認識できたと思っています。今後はロードマップを実現していく活動をしていき、データ・デジタルを活用し、地域のお客さまの課題解決に繋がる活動をしたいと思っています。
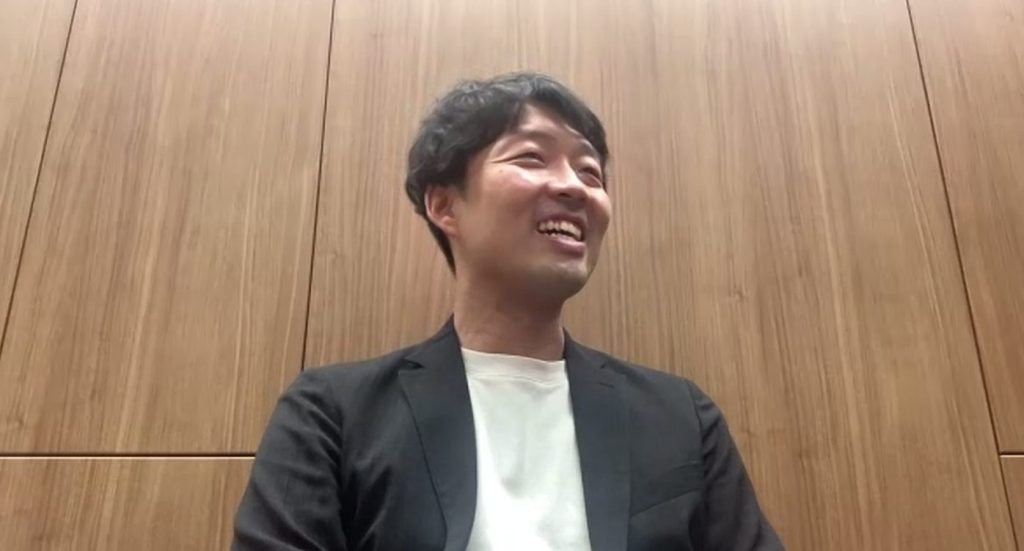
中国銀行/松田氏 私の野望は「地域の顧客に寄り添うOne to Oneマーケティング、地銀ナンバーワン」を実現することです。今は私たちがご教示いただく側ですが、どんどん吸収していきながら自分たちもしっかり取り組みを考えて、私たちがアドバイザー側として声を掛けていただけるような立場になることを目指したいと思っています。
DOORS 新たなフェーズに挑む今回のようなプロジェクトを遂行する前提条件としては、どのような事柄を重視すべきなのでしょうか。
BP/小川 失敗は悪いことではないという認識を持つことが重要です。
PDCAを機能させるには、まず失敗を認識することが出発点になります。失敗を認識してこそ改善のサイクルは回ります。失敗を否定的に捉えると、その循環は止まってしまいます。
失敗が許されるような社内文化を醸成し、失敗は決して悪いものではないという前提で取り組むことが、効率的かつ高速でサイクルを回すための重要な条件だと考えています。
中国銀行/小野氏 さらなる成長や発展のためには、失敗を恐れずにチャレンジすることが必要不可欠だと認識しています。新たな挑戦には失敗は付き物でしょう。失敗したら失敗の原因を分析して、次の行動につなげるということを繰り返していくしかないと思っています。
今回のプロジェクトでは、りそなさまとブレインパッドさまが伴走してくださっているので、失敗もしつつ、アドバイスをいただきながら取り組んでいきたいですね。
DOORS りそな さまにご質問ですが、金融業界全体のデータ利活用の底上げを意識した活動という意味では、今回のプロジェクトをどのように受け止めていらっしゃいますか。
りそな/扇田氏 金融業界では、今かなり厳しい競争が生じています。フィンテックや他業界からの参入なども競争激化の要因のひとつです。銀行同士がオープンに知見を共有し合えるようなプラットフォームを意識しなければ、参入してきた新しい会社にどんどんシェアを取られてしまうリスクもあります。
中国銀行さまに対してりそなが知見を共有することで、戦略実現に向けたさまざまな打ち手の可能性を提供できたと思っています。自社のマーケットだけでなく、他行さまのマーケットも広げることで、銀行間の協力体制が構築できると思っています。
DOORS では最後に今回のプロジェクトに対する、中国銀行さまの率直なご評価をお聞かせいただけますか。
中国銀行/奥川氏 私自身の認識が足りていなかった部分があり、当初は苦労したこともあったのですが、最終的にはいっしょにやらせてもらって本当に良かったと思っています。データ利活用領域の認識が高まりましたし、今後どうしたいのかという自分の考えを深めることもできました。
中国銀行/松田氏 ブレインパッドの加藤さんと小川さんのユーモアあふれるお人柄のおかげで、円滑にコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めることができました。その中でも、言うべきことははっきり言っていただき、いろいろとご指導していただいたと思っています。
行内の取り組み状況について第三者的な視点からご意見をいただき、One to Oneマーケティングのさらなる高度化に向けた有益なロードマップが作成できたと思います。
中国銀行/田尾氏 ブレインパッドさまとりそなさまには、いろいろと手を動かしていただき、ご知見を提供いただきました。我々が今までやってきたことが整理でき、足りない点やこれからの取り組みを明確にできたプロジェクトだったと思っています。ここで得たものを、今後のマーケティング施策に活かしていきたいです。
中国銀行/小野氏 我々の取り組みを深掘りしていただき、明確な評価を伝えていただけたので、手探りでやってきた部分がクリアになりました 。デジタルマーケティングのさらなる高度化に向け、ブレインパッドさまとりそなさまに伴走していただいた今回のプロジェクトは、地銀業界全体のベンチマークとなるものだと考えています。
りそなさまにはこのプロジェクトで、期待していた以上のご支援をいただいたと思っています。具体的なアドバイスやノウハウを提供してくださり、たいへん勉強になりました。感謝しています。
りそな/長谷川氏 こちらこそ、ありがとうございました。今回はサポートさせていただく立場ではあったのですが、お互い切磋琢磨しながら、さらに成長していければと思っています。
DOORS 本日は皆さま、興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
あなたにオススメの記事

2023.12.01
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24
【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08
DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23
LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22
生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説

