メルマガ登録
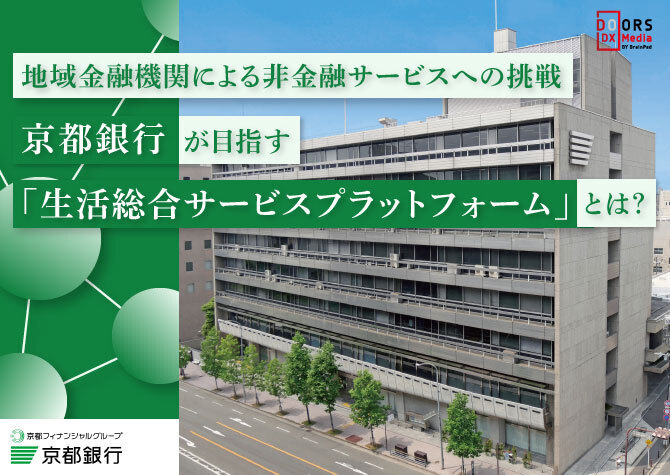
2023年4月から始まった「新・第1次中期経営計画(以下、中計)」で「総合ソリューション企業としての『新たな成長・発展のステージ』」への移行を宣言した京都銀行。中計の主要テーマのひとつに掲げる「DX推進」に関する取組みである「生活総合プラットフォーム」を実現するための重要なツールのひとつとして、Rtoasterが選定されました。
Rtoasterを導入したねらいは何か、具体的にどのように活用しているか、最終的にはどのような地域貢献を目指しているのか――京都銀行 イノベーション・デジタル戦略部の浅野氏と井上氏に話を聞きました。




株式会社ブレインパッド・DOORS編集部(以下、DOORS) 浅野様と井上様のご経歴や役割などについてご説明をお願いします。
京都銀行・浅野慎悟氏(以下、浅野氏) 2006年に京都銀行に入行し、京都市内の営業店で勤務した後、本部の営業部門で法人営業を経験しました。その後、現在の営業本部(旧法人部)の企画部門にて法人向け融資商品・サービスの企画・推進業務に従事し、2021年7月より現在まで、イノベーション・デジタル戦略部に在籍しています。

当部で策定したデジタル戦略に基づいて、従来から対面で築いてきた地域やお客さまとのつながりを、今後はデジタルの力でより強固にしていくことを目指しています。地域やお客さまの成長と京都銀行の成長を両立させるために掲げているのが、すべてのお客さまとデジタルでつながる「デジタルコネクト」という方針です。
この方針を実現するデジタル基盤として、個人向けには「京銀アプリ」、法人向けには「京銀ビジネスポータルサイト」といったサービスを提供しています。
私はこれらの個人向け・法人向け両方のデジタルサービス企画・推進を統括する立場にあります。また、社内のDXマインドの醸成も重要であり、DX人材の育成研修などにも携わっています。
「新・第1次中期経営計画」(2023年4月から2026年3月)で当行が目指す姿として、「地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する総合ソリューション企業」を掲げており、その実現のために、グループ総合力の強化、コンサルティング強化、人的資本経営の実践、DX推進の4つを主要テーマとした計画実現を進めているところです。
DX推進としては、先ほど述べた「デジタルコネクト」のさらなる加速と、データドリブン経営への変革を大きな柱として、現在も推進しています。
京都銀行・井上莞司氏(以下、井上氏) 2017年に京都銀行に入行し、営業店に配属されました。最初は京都市内の店舗、続いて大阪方面の店舗を経験した後に、2021年7月、浅野と同じタイミングでイノベーション・デジタル戦略部に配属されました。

私は配属時から個人向けサービスを担当し、「京銀アプリ」でどんなことができるかを考え、金融以外も含めたお客さまとの接点を増やしたり、取引を増やしたりするために必要なことをゼロから検討する役割を担っています。
DOORS ブレインパッドの2人は、今回の案件にどのように関わっているのでしょうか。
株式会社ブレインパッド・松田淳一(以下、松田) セールス&マーケティング・ユニットに所属しており、さまざまなお客さまのデータ活用やマーケティング施策などを支援する立場です。中でも、今回導入いただいたRtoasterを中心に、課題やご要望に対するご提案を行っております。

本案件については井上様からご相談をいただき、Rtoasterを活用した実現方法を技術面を含め何度もお話を重ねてきました。
株式会社ブレインパッド・星野賢太郎(以下、星野) 松田と同じセールス&マーケティング・ユニットに所属し、主には金融系のお客さまを担当しております。

松田はRtoasterの提案から導入まで、私は導入後の運用やフォローを担当しております。
DOORS 今回、バンキングアプリ上の非金融サービスで地域を活性化させるということが大きなテーマでした。なぜ非金融サービスに取り組むことになったのでしょうか。
浅野氏 従来の金融サービスだけを提供するビジネスモデルでは、今後多様化、高度化していくお客さまのニーズに対応しきれなくなるという危機感がありました。実際にさまざまな異業種が、生活に溶け込むようなサービスを起点に利用者を増やし、その後金融サービスにも拡張していく例が増えています。
何もしないでいたら、新しい業態のプレーヤーに取引機会を奪われるリスクがあります。そこで金融分野だけではなく総合ソリューション企業を目指して、積極的に事業領域を広げ、お客さまとの接点・サービス提供を維持拡大していきたいと考えました。それが、生活総合サービスプラットフォームを立ち上げた背景です。
DOORS 「生活総合サービスプラットフォーム」を始めた背景や位置づけを教えてください。
浅野氏 お客さまの真のニーズは、金融ニーズが発生する前の、お客さまの生活の中にあります。例えば、銀行に住宅ローンのご相談でお越しになる時点で「家を購入する」ということは決まっています。その後、お客さまはどこでローンを借りるかを検討され、京都銀行が選択肢に入っていた場合にのみ当行にご相談いただけることとなります。
例えば、ライフプランシミュレーションをご利用いただいたお客さまでは、住宅購入時期をご登録いただいている方もいらっしゃいますし、家族構成や現在の居住スタイルからご自宅を購入されるニーズの発生を予測することができます。お客さまが建築・不動産会社に相談する前にお客さまとの接点を作ることで、金融サービスへつなげるビジネスモデルを構築したいのです。
つまり住宅ローンで言えば、ご自宅を建てられる前の段階で、お客さまと接点を作ることで、京都銀行に住宅ローンのご相談をいただける可能性が高まるというイメージです。
DOORS 金融サービスの相談があるのを待つのではなく、もっと早い段階からお客さまとの接点を確保するようなサービスを拡充して、接点を広げることで最終的に金融収益につなげていこうという考え方ですね。
こういった取り組みをしている銀行は他にもあるのでしょうか。
浅野氏 私たちが進めているような「生活総合サービス」という形で、いろいろなコンテンツやメニューを総合的に提供している銀行は、まだあまり多くないと思います。部分ごとに、「住まいに関する相談を受けられる」、「ライフプランシミュレーションを提供する」という例はあるかもしれませんが、総合的に提供されているケースはまだ少ないのではないでしょうか。
星野 新しいと感じるのは、広告事業として地域の企業やお店の広告をアプリ内で出したり、クーポンをアプリで提供したりといった、すべてをひとつにまとめて提供していることです。とても先進的な取り組みだと思います。
松田 プロジェクトのキックオフ時に、当時のプロジェクト責任者の方が「規制緩和によって広告事業を地方銀行本体で扱えるようになってからまだ例の少ないケースだ」と話されていましたよね。
井上氏 地域金融機関がアプリで展開する事例としてはかなり早い方であったと思います。
松田 経験のないことにチャレンジするということで、意欲的に取り組んでおられたのが印象的でした。
DOORS 規制緩和とは具体的にはどのようなものですか?
井上氏 2021年の銀行法改正で、銀行本体が広告事業を行ってもよいと明記されました。
それまでも、デジタルサイネージやATMなど、銀行の既存資産を使った広告を付随業務としてやっていた銀行もありましたが、この改正でさらに踏み込んだ取り組みが可能になったのです。
DOORS プロジェクト立ち上げ当初に苦労されたことは何だったのでしょうか。
井上氏 私個人としては、営業店での勤務経験しかなく、本部での仕事も慣れない中、加えて行内でも、まだ実績が少ない非金融×デジタルの分野での挑戦となったため、当初は進め方にとても苦労しました。
しかし、サービスデザインのコンサルに協力いただいたり、システム開発ベンダーにプロジェクト進行部分も協力いただいたりと、外部の力も借りながら無事に立ち上げることができました。
DOORS 2021年からの取り組みだったということは、コロナ禍真っ盛りの中で立ち上げられたということですよね。
井上氏 そうです。コロナ禍だったために、営業店や本部の有識者を集めたアイデア出しのためのワークショップが大規模にできなかったという苦労もありました。ですが外部との打ち合わせはオンライン中心で進められたので、逆に助かりました。
浅野氏 広告サービスに関して、銀行が持つお客さまの情報を活かした広告サービスにしたいという思いから、アプリ広告はターゲティング広告が可能なメニューも提供しています。
お客さまの居住エリアや年代、興味・関心ごとなど、複数の切り口で広告を出し分けるのは、仕組みとして複雑ですが、その分独自性が出せると考えました。立ち上げ時は大変でしたが、ターゲティング広告を導入したことで、銀行が広告サービスを提供する価値が出せたと思います。
DOORS ターゲティング広告をやろうというのは当初からのアイデアでしたか。
井上氏 いいえ。最初は個人向けの生活サービスを拡充して、アプリの魅力を高めることが主な目的でした。その結果、金融関連のデータだけでなく、生活周りのデータが取得できるようになり、お客さま一人ひとりに合わせた広告を出せるという強みが生まれました。
つまり周辺データを取得できるようになったことで、結果的にターゲティング広告に発展させたということです。ユーザーである地元の中小企業や個人事業主など、広告に不慣れな事業者でも使いやすいよう、低価格で簡単に利用できるメニュー設計と操作性を意識しています。
同じプラットフォーム内にクーポンやオンラインモールなど複数のサービスがあるので、それらを組み合わせて、認知向上や販売促進をサポートしたいというねらいもあります。
DOORS 広告サービス以外の、地元企業様との新しい取り組みを教えてください。
井上氏 地元の企業様に協力いただき、毎月1、2分で読めるぐらいのコラムを発信しています。
お客さまが興味を持つコンテンツを提供することで、直接金融にはつながりませんが、アプリの利用活性化につなげようというねらいがあります。
今後はこのような事例をもっと増やしていくことを考えています。地域に根ざした銀行として、幅広い分野での情報発信ができるよう取り組みたいです。
DOORS 今回レコメンドエンジンとしてRtoasterを選定していただきました。選定した理由を教えてください。
井上氏 アプリで収集した行動データやシミュレーションの入力データ、それに銀行がもともと保有しているデータを掛け合わせて、金融商品や広告をレコメンドしたいという考えがまずありました。
それを実現できるツールとして、3つほどのMAツールをシステムベンダーと一緒に検討しました。その結果、Rtoaster action+(アクションプラス)が使いやすく、当行のニーズにも適合しているということがわかりました。
DOORS 選定基準を教えてください。
井上氏 まずは「実現性」を最優先しました。金融商品の提案をするだけなら多くのツールがありますが、今回は広告サービスも含んでいます。さまざまな企業からの申し込みデータとの連携や、画面のどの場所にどのように出すかなど要望が多く、それらにまとめて対応できるツールが必要でした。
一方で、銀行・グループ会社が保有する全てのデータを1カ所に集めたデータ基盤を作る構想が別にあったので、包括的なシステムだと費用面や運用面で負担になります。データ基盤にaction+単体を連携させることで、やりたいことが十分実現できる点が決め手になりました。
さらに、他の金融機関での導入実績があったことも、銀行としては大きな安心材料でした。
DOORS 実際活用してみての評価や感想をお聞かせください。
井上氏 実際に活用してみて、当初やりたかったことは問題なく実現できています。今のところ不満はありませんが、今後さらに細かく配信を制御しようとすると、オプション機能や別のツールが必要になるかもしれません。
例えば、広告が画面に表示されたら1カウントにするなど、厳密に数える場合はアドサーバーなどを組み合わせる必要が出てくる可能性があります。ただし、まだ具体的に決定したものはありません。現状は、知識や情報が増えてきたことでいろいろなことができるとわかってきた段階です。
DOORS Rtoasterを活用した広告サービスについて具体的に教えてください。
井上氏 Rtoasterは、主に広告の配信で使っています。広告のメニューとして、エリアが選択できるメニューと興味、年代が選択できるメニューがあります。企業がエリアと興味、年代を選択すると、該当するユーザーがアプリに訪れた際に、登録している広告アイテムを表示するようになっています。
アプリで取得したデータだけでなく、銀行の既存データもRtoasterに連携して、出し分けを実現しています。
DOORS ライフプランシミュレーションの取り組みと成果について教えてください。
井上氏 ライフプランシミュレーションへ入力された結果に応じて、お客さまごとにお勧めの金融商品や企業の広告を出しています。まだシミュレーションの利用者が少ないので、利用者数を増やして、金融商品につなげたり、広告の魅力を高めたりしたいと考えています。
DOORS Rtoasterの他の活用方法はありますか。
井上氏 ログデータを月次で受け取り、分析ツールに流しています。今後は分析結果を次の施策立案に活用していきたいと考えています。
DOORS 具体的にどんな分析をされているのでしょうか。
井上氏 アイテムごとにどんな属性の人がクリックしたかを把握して、金融商品のレコメンドの精度を向上したり、広告を出稿いただいた企業へのレポートの魅力を高めたりできないかなどを検討しています。
DOORS Rtoaster活用を進めた結果、どのような姿を目指したいというビジョンはあるのでしょうか。
浅野氏 バンキングアプリのユーザー数を増やすだけでなく、アクティブ・ユーザーを増やすために、魅力的なコンテンツを拡充していきたいと考えています。アクティブユーザーが増え、One to Oneのマーケティングを行うことで、金融取引の拡大につながり、お客さまとの結びつきを深めていくことを目指しています。
井上氏 どんなコンテンツがあれば毎日使っていただけるか、利用頻度を上げられるかを常に考え、試行錯誤して満足度を高めていきたいです。
DOORS Rtoasterは行内の連携についても活用されているのでしょうか。
浅野氏 サービス検討段階から今まで、基本的にはイノベーション・デジタル戦略部が主体で進めてきました。つまりデジタル戦略の施策として生活総合サービスを始めたので、当初は営業部門との連携があまり進んでいないことが課題でした。
ただ、生活総合サービスで使用しているRtoasterのようなツールは、他の営業施策にも活用できる場面が多いはずです。せっかく導入したので、営業部門との連携を強化して、Rtoasterの活用シーンを増やしたいと考えています。
最近では、ブレインパッド様も交えて、営業部門の担当者と「どんな活用方法があるか」を検討するミーティングを重ねています。
並行して、アプリ上のサービスを拡充して、お客さまの利便性や体験価値を高め、結果的に銀行の収益にもつながるサイクルを作りたいと考えています。
星野 Rtoasterの活用では、他行の場合、金融商品の訴求が主流です。京都銀行様は生活総合サービスの中で多様なレコメンデーションを行っており、これは新しい活用の方法であると考えています。一方で、もちろん金融商品のレコメンドにも活用が可能ですので、営業部門との連携強化に向けて、引き続きブレインパッドとしてもご支援できればと考えております。
営業部門との連携を進めるにあたっての課題や現在感じていることはございますか?
浅野氏 営業部門からのRtoasterの活用への関心も高まってきています。一方で、新たな施策の検討や導入に向けた動きが現場までスムーズに進みにくいという課題もあります。
こうした状況を踏まえ、まずは小規模な取り組みからスタートして効果を見える化し、営業部門内での認知や優先順位を少しずつ高めていくアプローチが有効ではないかと考えています。
取り組みの価値を共有しながら、着実に進めていきたいと考えています。
星野 関係するベンダーも多く調整には一定の時間を要するとは思いますが、引き続き丁寧な情報共有と連携を重ねながら、よりよい活用に向けてご支援していきたいと考えています。
DOORS 非金融サービスへ挑戦する銀行として、今後の目指す姿を教えてください。
浅野氏 今進めている生活総合サービスをさらに拡充し、より多くのお客さまに、金融以外の面でもアプリやポータルサイトを使っていただけるようにして、顧客接点を拡大していきたいです。
当行だけで進めるのではなく、地元企業や自治体などとも連携しながら、地域・社会にとって価値のあるサービスやメニューを展開できればと思っています。
DOORS 他の地域銀行との協業はいかがでしょうか。
浅野氏 今後の取り組みのひとつとして、同じような課題を持っている地域金融機関は多いはずなので、横の連携もしながらサービスを拡充できる可能性を探っています。
今までどおりの銀行サービスを提供しているだけでは、事業として縮小していくしかないと考える地方銀行も多いでしょう。共通課題を持つ金融機関同士が連携しながら、必要に応じて情報交換や協業などを行って、お客さまにより良いサービスを提供できればいいなという思いがあります。
DOORS リリースしてから1年半ほど経ちました。地域の企業様との関わり方などで変化がありましたか。
井上氏 広告サービスに参加いただいている企業は500社以上になっています。地域の個人と企業をつなぐ役割を一部担えているのではないかと思います。
DOORS このサービスが地域や企業とつながりを作る上で、今後どんな貢献ができると感じていますか。
浅野氏 今はバナー広告をアプリ上に出して終わりになっているケースが多いです。将来的には、例えば家を探している人なら「ここがお勧めですよ」というように、より適切な情報やサービスを提案できるようになるといいですね。
そうなれば金融商品の選択肢だけでなく、住宅や介護など、地域の企業が提供しているサービスをまとめてご紹介できます。お客さまにとっても便利だし、地域の事業者にもメリットがあると考えています。
DOORS 他に、効果が上がったという事例はありますか。
浅野氏 営業本部と連携してNISAの営業活動にライフプランシミュレーションを組み込む取組みを進めています。それによって、単に商品を売るだけではなく、お客さまの生活やお考えの理解を踏まえた提案営業につなげる成功事例が増えつつあります。これはライフプランシミュレーションのひとつの成果と考えられます。
DOORS 最後に、デジタルによる地域社会の発展を目指した取り組みについて、メッセージをいただけますか。
浅野氏 私たちが作るプラットフォームを通じて、地域を盛り上げることが目的です。京都フィナンシャルグループのブランドメッセージとして、「新しい波を起こせ。」という言葉がありますが、本当に波を起こすべく、粘り強い取り組みを続けていきたいですね。
当グループだけのメリットではなく、お客さまや地元企業、地域そのものにどんな価値を提供できるかを重視し、皆が幸せになれる施策を実施していきたいと思っています。
DOORS 今のお言葉を受けて、ブレインパッドとしては今後どのようなご支援をしていきたいですか。
星野 私たちにも、データ活用を通じてビジネス発展を支援し、社会に貢献していきたいという思いがあります。京都銀行様におけるRtoasterのより良い活用が、結果として地域への貢献に繋がると考えておりますので、引き続きご協力させていただければと思います。
松田 アプリ上の行動データだけでなく、お客さまのデータやことよりモール上での行動データを掛け合わせることで、よりお客さまの解像度を上げることもできると思います。
そのような新しい取り組みにも引き続きご協力させて頂きたいと考えています。
DOORS 本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

あなたにオススメの記事

2023.12.01
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24
【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08
DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23
LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22
生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説

