メルマガ登録

2021年11月に3回にわたり開催された、経済産業省 中部経済産業局が主催した「DX推進ワークショップ」の全体コーディネートを担当しました。中部地方ということで製造業を中心とした中堅・中小企業の経営者やリーダー層が参加してくださって大いに盛り上がりましたが、いろいろと感じるところもありました。
※中部経済産業局主催「DX推進ワークショップ」の開催レポートはこちら
そこで、このワークショップの内容や当日あった質問、また私自身が得た気づきをもとに、日本の企業でDXを推進する「変革プランナー」を応援する記事を書きたいと思った次第です。
ワークショップは3回にわたって行われましたが、その全てを網羅するよりも、その中から変革プランナーにどうしても押さえてもらいたい急所中の急所だけをまとめることにしました。それでも全部で5回にわたる連載となりましたが、読者の皆さまができるだけ飽きないよう、DOORS編集部との掛け合いも含めた形式で進めていきます。
これから5回にわたって、企業の変革プランナーとしてDXを推進していく立場の方に、DXを進めるための急所中の急所について語っていきます。
今回は初回ということで、いまさらながら「DXとは何か?」ということについて、私のほうからいろいろとお話をしたいと思います。
通常こういう話をする際には、DXの定義から入っていくものですが、今回の講座の中では、あえてテクノロジーの具体的な話をしないことをまず宣言しておきます。
なぜか。DXというとテクノロジーの話だと「勘違い」している方が多いからです。特に日本には製造業の会社が多いのですが、IoTだ、RPAだ、製造機械にカメラやセンサーを取り付けてだという手法の話に終始してしまいがちです。
そうした創意工夫が無意味ではないのですが、それをもってDXと考えているのならいささかまずいのではないかと、私などは思ったりするわけです。
ですがテクノロジーの話を始めると、その「いささかまずい」方向に話が進みがちのです。だったら、いっそ最初からテクノロジーの話は無しで進めていきたいと考えた次第なのです。
DOORS編集部(以下、DOORS) なぜ、「いささかまずい」のでしょうか?
IoTでもRPAでもAIでもVRでもARでも何でもいいのですが、多くの企業がこうしたテクノロジーを導入しようとする動機が、コストダウンや効率化だからです。特に製造業はその傾向が顕著です。
コストダウンや効率化が悪いということはないです。でもそれらを何十年も散々やって来た結果が、今の日本企業の姿――イノベーションが起こらない、付加価値が生まれない、給料が上がらない――に繋がっているのではないでしょうか?
DXと言うからには、それがビジネスの価値を変え、ビジネスを進化させることであるべきです。そうでなければ「トランスフォーメーション」とは言えないでしょう。つまり目的(Why)が大切ということですが、日本企業はそうでなくても物(What)や方法(How)の話になりがちです。だから今回はあえてテクノロジーの話を封印したいと考えたのです。
DOORS 目的が大切という話は、DX以外でも至るところで聞かれます。もう何年もそんな議論が続いているように思います。なのに、なぜ今になってもそのような議論から抜け出せないのでしょうか?
直接の答えになっていないかもしれませんが、日本のERP導入の歴史について少し話をさせてください。
ERPに限らず、日本のIT導入というのは、主に海外製品を輸入して、日本向けにカスタマイズしてきたというのが、少なくともここ20年ぐらい変わらない傾向ではないでしょうか。
その際に、ERPというものがなぜこの世に存在するのかといったところまで掘り下げた企業は、日本には残念ながらほとんどありませんでした。私は2001年からコンサルタントをやっていますが、その間にもITバブルの崩壊やリーマンショックなど様々な出来事がありました。それらが原因で、断続的な不況が長らく続いていたこともあったのかもしれませんが、ERPを業務効率化、コスト削減の魔法の杖だと考える企業が、日本ではほとんどだった印象です。
しかしERPが作られた本来の目的はまったく違います。製造から販売までデータが一気通貫に繋がることによって、データや数値に基づく精度の高い意思決定を実現するのが、本来のERPの価値です。
ERPの導入が流行った当時、日本企業では「グローバライゼーション」という言葉が流行していたのを思い出してください。仮に日本とブラジルにまたがって経営していたとしたら、ERPのようなものがなければ、企業ガバナンスなど到底不可能だったわけです。正確な情報把握やレポートのスピード感といったことがERPの本来の価値なのです。
それがなぜか日本では効率化の道具になってしまいました。なぜでしょう?ちょっと考えてみてください。
DOORS 精度の高い意思決定がなぜ必要かと考えると、それは企業の価値向上だったり、ビジョンを実現したりするためではないでしょうか。ですが、日本企業の多くは、そのあたりをあまり考えてこなかったから?
良い視点ですね。Z世代が個性や多様性を大切にし、社会貢献に関心があると言われていますが、大学生の就職志望ランキングを見ていると、その会社が有名かどうかが相変わらず一番の関心事になっています。しかし海外、特に欧米では、企業のミッションやビジョンに惹かれて人が集まることが普通です。実際に働いてみて違うと思えば、すぐに転職する――人材の流動性が高いからできることではありますが、その会社で働くことが誇らしく感じられるとか、スキルアップに繋がるといったことが志望動機になっています。効率的な会社だから偉いといった考え方はあまり無いわけです。
一方で日本企業は、残念ながら事業と価値との接続性といった考えが弱いと感じます。「私たちは何者か?」といったことを企業サイドも従業員もあまり気にしていません。それで、「DXは目的が大事」ということが言われ続けてきても、なかなか浸透しないのだと思います。
しかし実際にDXがうまくいっている会社を見ると、この「私たちは何者か?」を大事にしている会社ばかりです。効率化がどうということよりも、私たちはどうやって世の中に新たな価値を提供し、人々をどのように喜ばせているだろうということを突き詰めて考えている会社が、DX優等生だと言えます。
あえてテクノロジーの話をしないというところから始まり、いつの間にか日本企業は何が苦手かというところにまで話が進みました。ここでいったん、DXの定義について考えることにしましょう。
例の『DXレポート』を読んで、「2025年の崖」までもう時間がないと焦っておられる方も多いのではと思います。
そのなかでも記載されていますが、DXの定義もさまざまな派生した定義が創り出され、その多くは具体的に利用するテクノロジーの内容を規定しているものが増えてきました(IoT、クラウド、ビックデータ、AIなど)。
これらベンダーや、ベンダーに近い調査機関がつくる新しい定義は具体的である一方でテクノロジーの話、IT導入の話に誤解されがちな傾向があります。ERPの場合も同様でした。しかしこうした言葉につい踊らされてしまう側にも問題があります。私たちブレインパッドは「内製化」をお勧めするのですが、その根底には、内製化できるぐらい強い企業にならないとDX化だろうと、それ以前のIT化だろうとうまくいかないという思いがあるのです。
ここではDXの提唱者である、エリック・ストルターマン教授が2004年にしたと言われる、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という定義を採用しましょう。言わば原点に戻るのです。
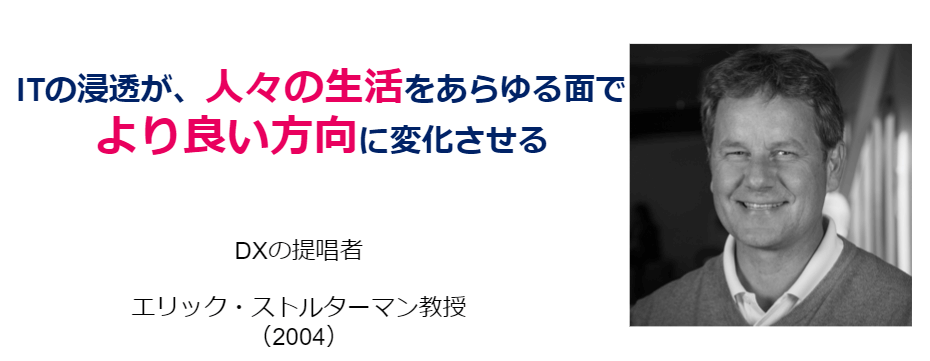
「人々の生活」に目を向けましょう。それを「あらゆる面でより良い方向」にということを、自社のビジョンやミッションと考えることにしましょう。そうすれば大切なことは、どんなテクノロジーを採用するかではないとわかるはずです。
日本は人口が減る一方で、マーケットが縮退していくことは間違いありません。しかしこのまま日本経済が一緒に弱くなっていくのが私たちの望むことなのでしょうか。
そうではないと思います。しかし効率化とコスト削減ばかり考えていれば、縮退は必然です。それはお金を節約し、使わないということですから、人口が減る以上に経済の弱体化を加速するだけです。
私たち日本人は新しい生活様式を生み出していかなければなりません。そこから新しいビジネスを生み出していかなければならないのです。付加価値を創り出して、市場と経済を大きくしていかなければ、本当に働く場所さえなくなってしまうことでしょう。
このことを日本人一人ひとりがもう一度よく考えるべきであり、DXはその機会を与えてくれたとプラスに捉えなければならないのです。
ではDXに取り組んでいると言っている企業は、実際にはどのようなことをしているのでしょうか?
具体的には、大きく5つの取り組みがあります。①オペレーションのデジタル化、②顧客接点チャネルのデジタル化、③意思決定のデジタル化、④サービス/製品のデジタル化、⑤新規デジタルビジネスの創出の5つです(図)。

数字が大きくなるにつれて付加価値と難易度が増大していきます。①、②は合理化であり、旧来のIT化と区別はありません。人によっては「デジタイゼーション」と呼び、DXに含めないかもしれません。③、④ぐらいになってくるとようやくDXらしい感じがします。⑤でようやく新しいビジネスを創出するという、私たちが「原点回帰」と呼んだDXの定義に沿うカタチになりますが、この段階に至っている企業はまだまだ少ないと言えます。
図では、左側を「社内業務」、右側を「顧客接点」と分けています。多くの企業ではDX推進において、従来のIT部門とは別に、DX推進部門を設置します。社内業務は主にIT部門、顧客接点は主にDX推進部門の管轄になることが多いと言えます。
顧客接点のほうが社内業務よりも価値を生む分、重要だと考えがちですが、両社のバランスが取れていることがより重要です。例えばある会社で、顧客の便宜を図ろうとウェブで窓口予約システムを導入しました。予約さえしていれば、顧客は待たされなくて済みます。つまり顧客の無駄な時間を減らそうというもので、その目的自体に何ら問題はありません。しかし実際に予約をしようと思ったら、3日先まで予約で埋まっていたらどうでしょうか? 3時間ぐらい待ってもいいから、窓口に行こうと考える人も出てきますよね。
いくら顧客のことを考えたとしても、それを可能とする社内業務の再設計が成し遂げられていなければ、何の価値もないどころか、むしろ顧客の不満を増大するだけになることさえあるわけです。
DOORS IT部門からしたら、その図に書かれていることを実現するだけでも大変なのではないでしょうか。私がIT部門の人間なら「ちょっと勘弁してよ」と思うぐらい盛りだくさんです・・・。
確かにおっしゃる通りです。しかし全部をやる必要もないことが多いのです。ありきたりですが、まずは優先順位を付けて、優先度が高いこと、より多くの価値を生むことから始めるべきでしょう。
もう1つ、ここでも日本企業が苦手なことを克服する必要があります。それはいったん始めたことでも必要がないならやめるということです。私は外資系企業にいたので、痛感するのですが、日本企業はこのことが本当に苦手です。例えば5人ぐらいのチームが年に2回しか見ないレポートを残すか残さないかといったことに、そのレポートを見る以上の工数をかけて議論したりします。外資系なら考えられないことで即終了です。
そもそも海外企業は、極端に言えば朝令暮改など当たり前で、方針も組織もころころ変わります。社員も慣れてしまって、変化に対する受容性が高いです。しかし日本企業は一度始めてしまうと、なかなかやめるということができません。日本の仕事の中でも撤退プロジェクトのリーダーが一番大変だとよく言われます。
しかしそれこそ労働人口が減ってきていて、多くの企業が人手不足に陥っています。新しい人材を採用することもとても難しくなっています。新しいことをやりたければ、何かをやめるしかないのです。
とはいえ、現場のほうからやめるというのはなかなか言い出しにくいのも確かです。だから経営者に「やめる」と意思決定して欲しいのです。付加価値を生むことにフォーカスして、それ以外はやらないという会社が、今のマーケットでは存在感を発揮しています。こうした意思決定ができない会社には、そもそもDXは難しいでしょう。
この記事の続きはこちら
変革プランナーにとってのDX推進の急所~第2回 DXと今までのIT活用の大きな違い~
あなたにオススメの記事

2023.12.01
生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24
【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08
DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23
LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22
生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説

